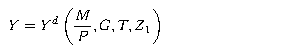グッドチャイルドによれば、モダニズムは分断され均一的な都市の風景を生み出しており、その都市計画は都市のエコシステムから切り離された対象としてその建築物を扱っていた。モダニストによる都市計画の問題の1つは居住者の視点や世論の動向を軽視している点にあり、第二次世界大戦以降の都市が直面している問題であるスラム、過密化、悪化したインフラ、汚染、病気について詳しく知らない裕福なエキスパートといったマイノリティによる都市計画がマジョリティに押し付けられていたことが指摘されていた。これらの問題はモダニズムが解決するはずの都市の問題であったが、たいていの場合、都市計画における全てに対応するはずのアプローチは失敗しており、他方で住民は建築のエキスパートにのみ委ねられていた過去の決定の内容に関心を示し始めていた。そしてアーヴィングによれば、1960年代の都市計画における伝統的なエリート主義やテクノクラートによるアプローチに対抗するために住民参加型の都市計画が登場していた。さらに1960年代の都市計画の担当者によるモダニズムの欠点に対する歴史的評価によって、都市計画の関係者を拡大することを狙った住民参加型の都市計画が支援されていた。
そしてポスト構造主義者の著作は知識に対する体系的な視点の中に多様な分野からの主張をまとめていたが、学際的な構造主義者は、学際性を主張しているにもかかわらず、専門分野の枠組みを好ましく考えており、研究対象を分析するためのアプローチに対して他分野からの視点を介在させない専門分野の独立性に固執する傾向にあった。また構造主義者と異なりポスト構造主義者は、ある現象に対する複数の関係から成り立っているシステムを絶対視しておらず、独立した自己充足的な要素から成り立っている現実を反映したものというよりむしろある主張の狙いの帰結として複数の関係やシステムを認識する傾向にあった。
ポストモダニズムは第二次世界大戦後に認識されていたモダニズムの失敗に対する反応から生じており、モダニズムの芸術におけるラディカルなプロジェクトが全体主義に結びつきながら主流の文化に融合されていったことが指摘されていた。ポストモダニズムと呼ばれるものの萌芽は1940年代に散見されており、ホルヘ・ルイス・ボルヘスが有名であった。しかし今日の多くの研究者は、1950年代後半にポストモダニズムがモダニズムと齟齬をきたし始めており、1960年代に優勢な地位を占めていったことに対して意見が一致していた。その後ポストモダニズムは、異論があるものの、芸術、文学、映画、音楽、ドラマ、建築、哲学において支配的になっていった。
そして1990年代後半以降の大衆文化やアカデミズムの世界においてポストモダニズムが廃れてきているとの考えが広まり始めていた。しかしポストモダニズムを継承する時代の名称や枠組みを定める取り組みはほとんどなく、提唱されていた名称も多数派からの支持を得ていなかった。
何が時代を形成しているのかについてのコンセンサスが得られておらず、時代自体がまだ始まりの段階にあった。しかしながらポスト・ポストモダニズムの枠組みを定める取り組みにおける共通のテーマは、信頼、対話、成果、誠意がポストモダンのアイロニーを超越して機能することにあった。
ポストミレニアリズムという語は2000年にアメリカの人文系の研究者であるエリック・ガンズによって紹介されており、倫理学や政治社会学におけるポストモダニズムに続く時代が示されていた。ガンズはアウシュビッツや広島の経験によって明らかになった加害者と被害者の倫理観の対立に基づく被害者を過度に偏重した考え方とポストモダニズムを密接に結びつけていた。ガンズの視点によれば、ポストモダニズムの倫理観は被害者の周辺に視点をおき、加害者側のユートピアを軽蔑することから生じていた。この意味におけるポストモダニズムは、近代のユートピアや全体主義に反対することについては有益であったが、和解のために長期的に役に立つ資本主義やリベラル・デモクラシーについて有益とならず被害者を過度に偏重した政治観によって特徴付けられていた。ポストモダニズムと比較して、ポストミレニアリズムは被害者を過度に偏重した立場をとらないことによって特徴付けられており、被害者を過度に偏重しないダイアローグを採用していた。
2006年にイギリスの研究者であるアラン・カービィはスードモダニズムと呼ばれているポスト・ポストモダニズムに対して社会文化的な評価を行なっていた。カービィはインターネットによって実現された文化の1つである世界一斉に表向き何かに直接関与する行為によって生じているうんざり感や中身の浅薄さとスードモダニズムとを関連付けており、スードモダニズムの時代において、人々はスマートフォンを利用し、クリックし、文字を入力し、サイトを眺め、選択肢から何かを選び、サイトを移動し、ダウンロードするだけになってしまったと述べていた。
スードモダニズムにおける典型的な知的状況は無知、熱狂、不安として描かれており、実質を伴わず「超」の語がついただけの現状を生み出すだけであった。どうでもいいことに世界一斉に参加してメディアに簡単に煽られてしまう浅薄さによって生じていた帰結はモダニズム特有の強迫観念的な細かさやポストモダニズム特有のナルシシズムと入れ替わった有意義な情報や意思を伝えることも感情的な交流をすることもない状況でしかなかった。カービィは美学的に価値のある結果がスードモダニズムから生じることはないと認識していた。
2010年にティモーテウス・バーミューレンとロビン・ファン・デン・アッカーはメタモダニズムをポスト・ポストモダニズムを巡る論争の行き着く場所として提案していた。ノーツ・オン・メタモダニズムの中で彼らは1980年代や1990年代のポストモダンの視点を生かしながら典型的な近代へ回帰する姿勢によって2000年代が特徴付けられていたと論じていた。彼らによれば、メタモダニズムの感性は、気候変動、金融危機、政情不安、デジタル革命のような現在のグローバルな状況に対する文化的な反応の特徴である多くの知識をもちながら知らないことも多く、プラグマティックな理想主義を示しているものとして考えられていた。彼らはポストモダン文化における相対主義、アイロニー、ゴチャ混ぜの文化が終焉を迎えており、積極的に関与し、共感し、中身を伝えることに価値を認めるポスト・イデオロギーの状況が生じていると述べていた。
バーミューレンとファン・デン・アッカーはメタモダニズムを多くの点の間を揺り動く振り子のようにモダニズムとポストモダニズムの間を揺れ動く心構えの構造として示していた。アートニュースの紙面におけるキム・レヴィンによれば、この揺れ動きは期待と落胆、誠意とアイロニー、愛情と反感、個人的な問題と政治的な問題、技術的観点とマニアの視点に対して等しく懐疑的な心構えを示していると思われていた。メタモダニズムの時代を迎えて、バーミューレンはかつてのメタナラティブが問題を抱えながらも必要とされており、理想がこれまでの歴史から信頼するに値しない幻滅の対象としてしか認識されない必然性はなく、愛情が馬鹿げた思い込みと必然的に同一である訳でもなかったことを示していた。
2006年にアムステルダム市立美術館とアムステル大学はダニエル・バーンバウムやアリソン・ジンジェラスによるリモダニズムについての講演会を開催しており、その入門編としてメディアでの言説に対抗しながら、本物のよさ、積極的な自己表現、芸術の自己肯定のような伝統的なモダニストの価値観への回帰としての絵画のリバイバルについての講演を行なっていた。
スタッキズムと呼ばれるムーブメントの創始者であるチャールズ・トムソンやビリー・チャイルディッシュはリモダニズムの時代を切り開いていた。2000年3月1日にリモダニストによるマニフェストが公表されており、それは芸術の理想、本物のよさ、積極的な自己表現を肯定しており、絵画に力点を置きながらも芸術に新たな精神を取り込んでいた。その前提はモダニストによる理想がまだ十分に生かされていないことであり、その目標はその理想が誤用されている現状においてその役割を回復させ、再度定義させ、リバイバルさせることにあった。リモダニズムは真実、知識、その内容を肯定しており、形式主義に疑念を抱いていた。
そのイントロとしてポストモダンの戯言によってモダニズムはその意味を見失っていたといった言葉が紹介されていた。そしてニヒリズム、科学的唯物論、方向性の定まらない破壊に対抗して勇気、個性、一般性、コミュニケーション、人間性を強調した14の視点を示していた。その中の7番目の視点は次のようなものであった。
精神性の追求は魂の旅であり、最初にやるべきことは真実と向き合うために暗黙の意味を列挙することであった。真実は今実際に存在しているものであり、願望とは異なっていた。精神性を追求する芸術家であることは、善悪、美醜、迷いや自信をはっきりと述べることを意味していた。
そのまとめとして、きちんとした心がある人々にとって、支配階級であるエリートによって創作された芸術が明らかにしているように、現在発表されている芸術が理性による成果の失敗を示していることは明白であり、その解決法は精神性を追求しているルネサンスにあり、他に芸術が歩むべき道は存在しておらず、スタッキズムからの提案は精神性を追求するルネサンスを今すぐに始めることであった。
2002年1月にマニフィコ・アーツはニューメキシコ大学の大学院生による「リモ:リモダニズム」と題された展覧会を開催していた。芸術家による講演会の場で、カリフォルニア大学バークレー校の教員であるケビン・ラドリーはリモダニズムは後向きではなく常に前を向いていると述べていた。展示会の寄稿文の中でラドリーは以下のように記していた。
...芸術家の主張に自信が取り戻されており、芸術家が皮肉、冷笑、教訓に煩わされることなく個性を追求することが可能であるといった視点が蘇っていた。その狙いは存在の意味を再び取り上げ、美の意味を練り直し、共感することの必要性を再度取り上げることにあった。
展覧会のキュレーターであるヨシミ・ハヤシは次のように述べていた。
リモはモダニズム、アバンギャルド、ポストモダニズム由来の考え方を混在させており、芸術に対するオルタナティブと主流派のアプローチを統合していた。リモでは多文化主義、アイロニー、高尚さ、アイデンティティに関する問題が取り扱われていたが、それのみで芸術を確立している訳ではなかった。伝統に対する再考と再定義は単なる脱構築によって成された訳ではなく、概念の接点を探しつなげることによって成されていた。定義によればリモは基本的に細胞に例えられており、そのルーツは芸術の周縁部分に由来していた。
2008年8月27日にジェシー・リチャーズはリモダニスト・フィルム・マニフェストを発表しており、そのマニフェストは映画における新たな精神性を追求しており、映画製作に直感を導入しており、リモダニストによる映画をむき出しで必要最小限で叙情的でパンクの要素を含む映画製作であると表現していた。
その後の2009年にマングビーイング誌におけるリモダニストによる映画についてのエッセイの中で、リチャーズはプロと関連させながらリモダニズムを論じていた。
一般的にリモダニズムはアマチュアによる挑戦を肯定しており、プロを考察の対象として特殊な立場に置いていた。つまりこれまでのプロは失敗をなくすために励む存在であり、それゆえプロフェッショナルであったが、私はそうは考えていない。そして仮にプロが絶えず成長する可能性を有する存在であるのならば、私はそのプロを支持したい。絵を描き、演技をし、他の芸術家のためのモデルになり、宗教の仲立ちをし、意識のレベルに影響することを行い、他者を不快にさせることに対しても一歩足を踏み出し、外の世界での生活に触れ合い、見知らぬ大海に飛び込むことを実際に自分でやる映画製作者を支持したい。私はそれらがプロにとっての挑戦だろうと考えている。
ポストモダニズムに対する批判は多様であり、ポストモダニズムが無意味であり、蒙昧主義にすぎないとの主張を包含していた。例えばノーム・チョムスキーは分析や経験を通じた知識に貢献していないことを理由にしてポストモダニズムが無意味であると主張していた。チョムスキーは「理論の原理は何か、どの事実に基づいているのか、何が明らかにされていないのか...と尋ねられたときに、なぜポストモダニストの知識人は他分野の研究者のように答えようとしないのか」と尋ねていた。そして「仮にその答えがないのであれば、私は情熱に対する類似の状況におけるヒュームからのアドバイスを送りたい」と続けていた。またキリスト教徒の哲学者であるウィリアム・レーン・クレイグは「私たちがポストモダンの文化の中で暮らしているというアイデアは幻想である。実際ポストモダンの文化はあり得ないものであった。そして人々に馴染まれるものではなかった。また科学、工学、技術の問題になると人々は相対主義の立場ではなかった。むしろ宗教や倫理の問題になったときに相対主義の立場を採用していた。そしてこの話から導き出されることはこのような立場はポストモダニズムではなくモダニズムであるということだ」と述べていた。
例えばイギリスの歴史家であるペリー・アンダーソンのような人々は、ポストモダニズムという語が有しているさまざまな意味が互いに矛盾し合っており、ポストモダニストを分析することが現代文化に対する洞察をもたらすだろうと述べていた。またカヤ・イルマズはポストモダニズムという語の定義が明確でなく筋が通っていないことを示していた。イルマズによれば、理論自体が反基礎付け主義であるためにポストモダニズムという語が基礎を有していないことが指摘されていた。
フレドリック・ジェイムソンによれば、ポストモダニティにおいて物事の尺度が喪失されており、ポストモダンの主体が我を見失ってしまうほどの多くの事柄の中に私たちが埋没してしまっていることが指摘されていた。この新たなグローバル空間はポストモダニティの正念場でもあった。ジェイムソンが認識しているポストモダンの他の特徴はグローバル空間における存在のある側面として示されていた。またポストモダンの時代は文化の社会的機能を変化させていた。ジェイムソンによれば、近代の文化は中途半端に自律的で、現実を超えた存在を仮定していたが、ポストモダンの文化はその自律性を奪っており、文化人の営みが社会全体を消費するまでに拡大しており、あらゆる人々が文化人になっていたことが指摘されていた。そして評論における物事の尺度であり左派の理論が依拠している巨大な資本という存在の蚊帳の外に文化が位置しているといった仮定は時代遅れになっていた。また多国籍資本の驚異的な拡大が資本主義に染まっていない地域(自然であれ意識であれ)を植民地化し尽くしてしまい、植民化される側は評論家にとって都合がよい状況を与えていたことが指摘されていた。
前回同様これが全てであるとは言及しないが、アメリカのWikipediaの「ポストモダニズム」、「ポスト・ポストモダニズム」、「メタモダニズム」、「リモダニズム」、「ポストモダニズムに対する批判」、「ポストモダニティ」、「ミシェル・フーコー」を訳すことにより上記の知見をサポートすることにする。URLは以下に示されるとおりになる。
http://en.wikipedia.org/wiki/Postmodernism
ポストモダニズム
ポストモダニズムは芸術、建築、モダニズムに対する批評をテーマにした20世紀後半のムーブメントの総称であった[1][2]。ポストモダニズムは文化、文学、芸術、哲学、歴史、経済学、建築、フィクション、批評における懐疑的な解釈を包含していた。脱構築やポスト構造主義とよく結び付けられる背景として、その語が20世紀のポスト構造主義的な思想の潮流とともに大きな人気を博していたことが指摘されていた。
ポストモダニズムという語は、モダニズム、つまりそれまでのスタイルを形成していた伝統的な要素に抵抗する芸術、音楽、文学のムーブメントを示していた[3]。
1 歴史
ポストモダンという語が初めて用いられたのは1870年代頃であり、ジョン・ワトキンス・チャップマンはフランスの印象主義から逃れる運動の一環として「絵画をテーマにしたポストモダンスタイル」を提示していた[4]。ザ・ヒバート・ジャーナル(哲学の季刊誌)に掲載された1914年の記事においてJ・M・トンプソンは、ポストモダンという語を宗教を批評する際の判断における変化を示すために用いていた。「ポストモダニズムの存在理由は、カトリックの伝統やカトリックの感情に対して神学が宗教をテーマとして取り上げるように、モダニズムに対する批評を徹底することによって、モダニズムにおける二項対立から逃れることにあった。」[5]
1921年や1925年にポストモダニズムという語は芸術や音楽における新たなスタイルを示すために用いられていた。1942年にH・R・ヘイズは新たな文学のスタイルとしてその語を用いていた。一方この語は1939年に歴史の潮流に対する包括的な理論として初めてアーノルド・J・トインビーによって採用されていた。「私たちが直面しているポストモダンの時代は1914年から1918年までの戦争によってすでに始まっていた。」[6]
1949年にポストモダニズムという語は近代建築に対する批判を示すために用いられており、その語はポストモダン建築をリードしており[7]、国際性を主張していた近代建築運動に対して呼応したものであった。建築におけるポストモダニズムは装飾を再評価し、都市建築において周囲の建造物を考慮し、装飾の歴史的な意味を重視し、直角や直方体に拘らない特徴を有していた。
1971年にICA(インスティテュート・オブ・コンテンポラリー・アート、ロンドン)で行われた講演の中で、メル・ボックナーは芸術における「ポストモダニズム」を解説しており、それが「初めて芸術のベースとしてセンスデータや単一の視点に依存することを否定しており、批評として芸術を捉えていた」ジャスパー・ジョーンズから始まっていたことを指摘していた[8]。
近年、ウォルター・トルーエット・アンダーソンはポストモダニズムを4つの世界観の1つとして示しており、(a)真実が社会的に形成されたものであると見做しているポストモダンのアイロニストの立場、(b)真実が確立された方法論やよく練られた研究を通じて得られるとする科学的合理性を重視する立場、(c)真実が欧米の文明の遺産の中から得られるとする社会的伝統を重視する立場、(d)真実が自然との調和を保つことによって得られるとし、内なる自分を精神的に探求する新ロマン主義の立場を挙げていた[9]。
哲学におけるポストモダニズムや社会・文化の分析は批評の意味を拡大しており、文学、建築、デザインの原点になっており、マーケティング・ビジネスや歴史、法、文化の解釈においてはっきりとした姿を示しており、それらは20世紀後半に生じていた。これらの展開、つまり1950年代や1960年代から始まり、1968年の社会革命をピークとしていた西洋の価値体系(愛、結婚、大衆文化、工業化からサービス化への経済シフト)に対する再評価はポストモダニティという語によって示されており、ポストモダンの思想に影響を及ぼした人の中に、ある視点や政治的・社会的動向から言葉の意味が一般的に影響を受けているといったポストモダニズムを論じていたパウル・リュッツェラー(セントルイスの)が含まれていた。またポストモダニズムはポストモダニズムを展開させたポスト構造主義といった語と交換可能であり、ポストモダニズムやポストモダニストによる思想を適切に把握するためには、ポスト構造主義者やその支持者たちによる思想を理解することが求められていた。そしてポスト構造主義は構造主義の時代の後に生じていたポストモダニズムに類似していた。ポスト構造主義は逆説的であるが構造主義を通じて分析している新たなアプローチによって特徴付けられていた[10]。「ポストモダニスト」という語はある政治的・社会的ムーブメントを部分的に表現しており、「ポストモダン」という語は1950年代以降のムーブメントを示しており、そのムーブメントを現代史の一部に組み込んでいた。
2 芸術への影響
2.1 建築
建築におけるポストモダニズムは近代建築における失敗した理想主義や停滞していた状況に対する自然な反応として始まっていた。ヴァルター・グロピウスやル・コルビュジエによって提唱されていた近代建築は理想的な完成型を追求しており、形と機能の調和を狙っており[11]、「浅薄な装飾」を否定していた[12][13]。モダニズムに対する批評家は、一般論としての完成像やミニマリズムを構成す要素が主観的な存在であり、近代のアナクロニズムであることを指摘しており、近代の哲学の業績に対して疑念を呈していた[14]。マイケル・グレイヴスやロバート・ヴェンチューリの作品を例に挙げればポストモダン建築は、建築で利用可能なあらゆる方法論、素材、色を活用しておらず、形としての「純粋さ」や「完成された」建築を追求することを否定していた。
モダニストであるルートヴィヒ・ミース・ファン・デル・ローエは「より少ないことは、より豊かなこと」であるといった言葉で知られており、ヴェンチューリは「少ないほど、退屈である」との皮肉で知られていた。ポストモダニストの建築は、古く「絶対的な」モダニズムに対して疑念を呈するための美に関するムーブメントの1つであり、個人的な嗜好や客観的で究極的な真実や原理の多様性を求めるものであった。
批評、懐疑主義、全体とのずれを強調することを主張することの中に、ポストモダニズムの美の特徴が現れていた。この意味でこの語を用いている人々の中に、チャールズ・ジェンクスがおり、アーキテクチュアル・デザイン・マガジンによればチャールズ・ジェンクスは「その後の30年間におけるポストモダニズムを示しており」、「80年代におけるポストモダニズムを体現している国際的に評価された批評家」であった[15]。
2.2 都市計画
ポストモダニズムは都市計画が社会的背景や合理性と無関係に広く採用している「全体主義的な特徴」を否定していた。この意味でポストモダニズムはモダニズムの後継ではなかった。1920年代以降の近代化のムーブメントは大量生産という新たなモデルに依拠したデザインや都市計画を求めており、大規模なソリューション、美の標準化、プレハブ工法によるデザインを採用していた(グッドチャイルド、1990年)。さらにモダニズムは個の違いを認識することに失敗しており、均一な光景を目標とした都市の生活を生み出していた(シモンセン、1990年、57)。モダニズムを通じて都市計画はカオス・不安定・変化の中で安定感があり、システマティックであり、合理性を追求した建築を確立しようとする20世紀のムーブメントを代表していた(アーヴィング、1993年、475)。ポストモダニズム以前の都市計画のプランナーは、唯一の「正しい方法」を通じて新たな建築物の設計を実現することに対して自負を抱いている「最も妥当なエキスパート」として認識されていた(アーヴィング、1993年)。そして同時に1945年以降の都市計画はデベロッパーや企業の利潤を確保するための手段の1つになっていた(アーヴィング、1993年、479)。
モダニズムによれば都市計画は分断され均一的な都市の風景を生み出しており、都市のエコシステムから切り離された対象としてその建築物を扱っていた(グッドチャイルド、1990年)。モダニストによる都市計画の問題の1つは居住者の視点や世論の動向を軽視している点にあり、第二次世界大戦以降の現実の「都市」が直面している問題、例えばスラム、過密化、悪化したインフラ、汚染、病気(アーヴィング、1993年)について詳しく知らない裕福なエキスパートといったマイノリティによる都市計画がマジョリティに押し付けられていたことが指摘されていた。これらの問題は正確にはモダニズムが「解決する」はずの「都市の問題」であり、たいていの場合、都市計画における「総合的で」「全てに対応するはずの」アプローチは失敗しており、他方で住民は建築のエキスパートにのみ委ねられていた過去の決定の内容に関心を示し始めていた。そして1960年代の都市計画における伝統的なエリート主義やテクノクラートによるアプローチに対抗するために住民参加型の都市計画が登場していた(アーヴィング、1993年、ハートゥカ、ドーヘ、2007年)。さらに1960年代の都市計画の担当者によるモダニズムの「欠点」に対する歴史的評価によって、都市計画の関係者を拡大することを狙った住民参加型の都市計画が支援されていた(ハートゥカ、ドーヘ、2007年、21)。
1961年のジェイン・ジェイコブズの著作である『アメリカ大都市の死と生』はモダニズムの枠組みの中で発達してきた都市計画に対する批判であり、都市計画におけるモダニズムからポストモダニズムへの移行を示していた(アーヴィング、1993年、479)。しかしモダニズムからポストモダニズムへの移行は1972年7月15日の午後3時32分に生じたのだと言われており、その理由としてプルーイット・アイゴーつまりル・コルビュジエの言葉である「住宅は住むための機械である」といった思想から影響を受けた建築家であるミノル・ヤマサキによって設計されたセントルイスの低所得者向けの住宅が無人化したことが挙げられていた(アーヴィング、1993年、480)。その後ポストモダニズムは多様性を考慮しながら、不確実性、柔軟性、変化をもたらしていった(ハートゥカ、ドーヘ、2007年)。ポストモダンの都市計画は複数性を許容しており、マイノリティや立場が弱いグループの主張を容認するために社会的な差異に対する認識を促していった(グッドチャイルド、1990年)。モダニティの枠組みに収まった都市計画についての言説には注意することが重要であり、確かに資本の論理によって展開していたが、事実としてポストモダニティは異なった状況の下で発展していった。モダニティは一般大衆と標準化された生産や消費を歓迎するフォーディズムそしてケインジアンのパラダイムの背後にある資本主義の倫理によって形成されており、一方ポストモダニティは資本蓄積、労働市場、組織のフレキシブルな姿から生じていた(アーヴィング、1993年、60)。そして「ネオコンの」ポストモダニズムと「抵抗する」ポストモダニズムの間にも差異が存在していた。「ネオコンの」ポストモダニズムはモダニズムを否定しており、新たな文化に統合するために失われた伝統や歴史を取り戻そうとしていたが、「抵抗する」ポストモダニズムはモダニズムを再構築し、失われた伝統や歴史に回帰することなくその原点を批判していた(アーヴィング、1993年、60)。ポストモダニズムの帰結として都市計画の担当者は都市計画を行う唯一の「正しい方法」に対して固執することなく多彩なスタイルや多様な「都市計画の方法論」を受け入れていった(アーヴィング、474)[16][17][18][19]。
2.3 文学
文学におけるポストモダニズムは1972年に登場しており、「ジャーナル・オブ・ポストモダン・リテラチャー・アンド・カルチャー」といったサブタイトルが付いたバウンダリー2の創刊号によって示されていた。デヴィッド・アンティン、チャールズ・オルソン、ジョン・ケージ、ブラック・マウンテン・カレッジの人々は当時のポストモダニズムを知的ないし芸術的に表現する代表的な人物であった[20]。そしてバウンダリー2は今日のポストモダニストに対して影響力を有していた[21]。
ホルヘ・ルイス・ボルヘスの短編である『『ドン・キホーテ』の著者、ピエール・メルナール』(1939年)はポストモダニズムを想定していたと考えられており[22]、究極のパロディであると考えられていた[23]。またサミュエル・ベケットはポストモダニズムの重要な先駆者であると考えられていた。そしてポストモダン文学に関連している作家の中に、ウラジーミル・ナボコフ、ウィリアム・ギャディス、ジョン・ホークス、ウィリアム・バロウズ、ジャンニナ・ブラスキ、カート・ヴォネガット、ジョン・バース、ドナルド・バーセルミ、E・L・ドクトロウ、ジャージ・コジンスキー、ドン・デリーロ、トマス・ピンチョン[24](ピンチョンの作品は「ハイモダン」として考えられていた[25])、イシュマエル・リード、キャシー・アッカー、アナ・リディア・ベガ、ポール・オースターが含まれていた。
1971年にアラブ系アメリカ人の研究者であるイーハブ・ハッサンはポストモダンの視点から文学を批評した初期の作品である『ザ・ディスメンバーメント・オブ・オーフィアス:トゥウォード・ア・ポストモダン・リテラチャー』を発表し、その作品の中でマルキ・ド・サド、フランツ・カフカ、アーネスト・ヘミングウェイ、ベケットらによる「沈黙の文学」や不条理演劇ないしヌーヴォー・ロマンの展開を表現していた。また『ポストモダニスト・フィクション』(1987年)の中で、ブライアン・マクヘイルはモダニズムからポストモダニズムへのシフトを描いており、ポストモダン以前の作品は認識論による支配によって特徴付けられていたが、ポストモダンの作品はモダニズムから発展していたものの主に形而上学に対する疑念に関連していると主張していた。そして次の著作である『コンストラクティング・ポストモダニズム』(1992年)を通じて、マクヘイルはポストモダンの著作やSFで知られている現代作家の作品に対する解釈を提示していた。マクヘイルの『何がポストモダニズムであるのか』(2007年)[26]は、ポストモダニズムを論じるときに現在時制の代わりに過去時制を用いる方が適当であるといったレイモンド・フェダマンの指摘に沿ったものであった。
2.4 音楽
ポストモダンの音楽はポストモダン期の音楽であり、ポストモダニズムが有する美学的ないし哲学的トレンドに沿った音楽であった。名が示すとおり、ポストモダニストによるムーブメントは部分的にモダニストによる理想に対抗しながら形成されていった。このためポストモダンの音楽はモダニストによる音楽に対する批判として定義されており、作品はモダニストによるものかポストモダニストによるものかの何れかであった。ジョナサン・クレイマーは、ポストモダニズム(音楽における)は表面上のスタイルや時代(つまり環境)の問題と言うよりむしろ考え方の問題であることを指摘していた。
ミニマリズムが登場した1960年代にポストモダンはクラシック音楽に対して影響を及ぼしていた。テリー・ライリー、ヘンリク・グレツキ、ブラッドリー・ジョセフ、ジョン・クーリッジ・アダムズ、ジョージ・クラム、スティーヴ・ライヒ、フィリップ・グラス、マイケル・ナイマン、ルー・ハリソンといった作曲家達はエリート意識に対抗して、シンプルなテクスチュアや適度に協和したハーモニーを有する音楽を作曲することによって、調性を放棄したモダニズムによる不協和音に抵抗しており、よく知られているようにジョン・ケージはモダニズムに共通した客観性に対するメタナラティブに疑念を呈していた。一部の作曲家達はポピュラーミュージックや民族音楽の考え方から広く影響を受けていた。
クラシック音楽に対するポストモダンの影響は音楽のスタイルのみに限定されず、ポストモダン期の音楽全般を対象にしていた。そしてポストモダニティがポストモダニズムを生み出したように、ポストモダンの音楽が生み出されていた。またポストモダンの音楽はモダニズムに抗うポストモダンの芸術に固有な側面(以下は訳者の注になるが、言い換えるならば芸術家にとっての副業の問題)を共有していた。その一例はTシャツを販売しているロックバンドになり、一見するとそれは本来の音楽活動に付随したビジネスであるのだが、Tシャツはバンドの音楽以上にポピュラーな存在であり、バンドの音楽以上に「クール」に思われていた。
しばしば古典派音楽やロマン派音楽に分類される作曲の枠組みに回帰しながらも、全てのポストモダンの作曲家がモダニズムの楽理を回避している訳ではなかった。例えばオランダの作曲家であるルイ・アンドリーセンの作品は反ロマン主義としての実験音楽の特徴を示していた。モダニズムの完成度の限界やその見かけの厳格さに対して妥協しながらも表現の自由を追求することは作曲におけるポストモダンの影響の特徴であった。
3 影響力のあるポストモダンの哲学者
マルティン・ハイデッガー(1889-1976)
「主観」や「客観」といった概念の哲学的基盤を否定し、正反対の論理的基盤によってその両者が影響を及ぼし合っていると主張していた。それらを理解するためにこのパラドックスを認める代わりに、ハイデッガーは「解釈学的循環」と呼ばれる理解のプロセスを通じてそれらを把握していた。ハイデッガーは歴史的事実や概念の文化的構築を強調しており、時間と無関係に存在している内在的理解の必要性を主張していた。ここでハイデッガーは、ソクラテス以前の哲学の中に示されていたもののプラトン以後陰りを示していた現存在に対する疑念を再度取り上げることが現代の哲学の仕事であると明言していた。この仕事は現存在や思想史において忘却されたものを突き詰めることによって部分的に果たされていたが、それは何が人間の類似点に対する基礎的条件を構成しているのかについて私たちが再度考えなければならないことを意味していた。しかしこのためには、歴史と無関係に自己に対して言及するときに、以下に述べるような人間の姿(について必ずしも固定した考え方ではないが実在を示しているもの)を容認する思考、感情、実践に関わることが求められており、その人間の姿は一般的な人間であることだけでなくその後の成長に伴う個々の人間の違いを含めた可能な経験や可能な存在を許容するものであった。そのような結論はハイデッガーをフッサールの現象学から自由にさせており、その代わりに(時代に逆行しているが)形而上学の問題への回帰を促していたが、この回帰は一般的に物自体と現象もしくは物自体と実際に現れている物(クオリアを参照せよ)を区別していなかった。そして現存在になるプロセスを取り上げることは物自体と現象のギャップに対する橋渡しとなっていた。これによればハイデッガーはロマン主義の哲学者であるフリードリヒ・ニーチェから影響を受けていた。合理主義、経験主義、方法論的自然主義が内在している主体と客体もしくは感覚と知識の区別に対するハイデッガーの批評はポストモダニズムの思想家に影響を与えており、事実が思考のプロセスと別に存在しているといった考え方を否定しており(しかしハイデッガーは唯名論者ではなかった)、哲学や科学での前提は社会の期待からの影響を受けており、概念は、歴史的な精神や変化する経験(ヨハン・ゴットリープ・フィヒテ、ハインリヒ・フォン・クライスト、コンストラクティビズムを参照せよ)から独立した論理的前提の派生物であることよりむしろ、実際に生じた歴史的な実践を表現したものであり、プラグマティストや悲観主義者の考えによれば、存在(拡大解釈すれば現実そのもの)は、控え目で肯定的で認められている状態、結果、実体そのものよりむしろ、行動、方法、方向性、可能性、疑問の提示であった(プロセス哲学、形而上学におけるダイナミズム。プラグマティズム、生気論を参照せよ)。
ジャック・デリダ(1930-2004)
テクストの構造的問題や哲学に対するその影響を再検討し、分析のためのアプローチとしての形而上学に疑念を呈し、ハイデッガーが用いた脱構築を出発点にして、デリダ流の脱構築はよく知られるようになっていった。デリダはハイデッガーのように前提と結論や表象の元と表象そのものの間の循環論法を示しているエポケーとアポリアのような哲学における懐疑論やソクラテス以前の哲学に関連したギリシア哲学に言及していたが、ジル・ドゥルーズに類似したアプローチでプラトン、アリストテレス、デカルトによる哲学を根本から再検討していた。
ミシェル・フーコー(1926-1984)
フーコーは、社会秩序の内部における意味、権力、社会的行動の関係を示すために(『言葉と物』、『知の考古学』、『監獄の誕生』、『性の歴史』を参照せよ)「エピステーメー」や「系譜学」のような概念を再検討していた。認識論におけるモダニストの視点と反対に、フーコーは、合理的な判断、社会的実践、「生権力」と呼ばれるものが不可分な関係にあるだけでなく、相互に関連した決定因子でもあると主張していた。フーコーは多くの進歩的な政治的動機を抱えており、極左のメンバーとの個人的な結びつきを保ちながら、当時の左翼の思想家と議論を交わしており、マルクス主義、左派のリバタリアニズム(例えば、ノーム・チョムスキー)の支持者、ヒューマニズム(例えば、ユルゲン・ハーバーマス)との緊張感を抱えながら、啓蒙時代の自由、解放運動、自己決定、人間の本性を示している考え方を否定していた。その代わりにフーコーは、そのような産物が文化的ヘゲモニー、文化的暴力、文化的疎外を助長していたシステムに着目していた。啓蒙時代のヒューマニズムが有する「肯定的な」主張を否定しながら、フーコーはジル・ドゥルーズやフェリックス・ガタリとともに反精神医学運動を精力的に行い、施設に依存した精神医学の現状を鑑みながら、精神分析の中心でありフロイトが示している抑圧された感情(フロイトが示している抑圧された感情といった概念は1960年代や1970年代にフランスで影響力を有していた)が誤りであったと主張していた。フーコーは論争を呼ぶ発言で知られており、彼の「言葉は悩みの種である」との発言は社会的な慣習を支える権力構造を損なうかもしれない無意味で誤った風潮を助長するように「言葉」が作用していることを意味していたが、そのような権力構造が権利の解放運動を支援しマイノリティを尊重しているときでさえもフーコーは同様の主張をしていた。そしてフーコーの著作はポストモダンの研究に大きな影響を与えていた。
ジャン=フランソワ・リオタール(1924-1998)
リオタールの思想は『ポストモダンの条件』の中でモダニズムを通じて人間科学が前提にしている考え方の危機を示しており、それらの問題は「コンピューター」化し「テレマティクス」化した時代の到来によって顕在化していた(情報革命を参照せよ)。アカデミズムにおけるこの危機は、研究の成果を肯定している暗黙の前提や価値観がもはや妥当でないかもしれないとの主張によって、18世紀後半以降の研究を正当化している価値観に対する疑念を呈していた(特に社会科学や人文科学において顕著であったが、リオタールは数学を例に挙げていた)。現実世界の問題に対する外形的な解釈は、結論の自動的な演繹、情報の蓄積、そしてそれらの検索と複雑に関連しており、そのような知識は情報の枠組みに含まれている知識人の手からますます「離れて」いった。知識は生産者と消費者の間で取引される商品に姿を変えており、それ自体が目的であるか自由や社会的便益をもたらすツールであることを否定しており、ヒューマニズムを肯定し超然とした側面を有することを否定されており、知識と教育の関係が遍在的で、具体的で、前提を課さない「データ」の交換として認識されていた[27]。そしてさまざまな学問分野でなされている主張の「多様性」が統合化された原理や洞察を欠いており、データベースを活用する研究が含意している内容の画一性を論じながら、研究の対象がますます専門分化を深めていったことを指摘していた。アカデミズムを擁護する価値観の前提はリオタールが人間の目的、人間の理性、人間の進歩に関する架空の想定であると考えていたものであり、この架空の産物をリオタールは「メタナラティブ」と呼んでいた。これらのメタナラティブは西洋の社会に深く浸透していたが、大学における急速な情報化の進展によってその基盤を揺るがされていた。知識人の洞察つまり人間の利益と真理に忠実であることを融和させた多様な知識を追求する理性から機械化されたデータベースや市場へと権威がシフトしていったことが、リオタールの視点によれば、知識の「正当化」の実態や人生、社会、価値に関する知識の理論的根拠を説明していた。現在の私たちは、コレクティブ・アイデンティティを規定する言語に表れない価値観に縛られることによってではなく、さまざまな「言語ゲーム」に自然に対応することを通じて行動する環境に置かれていた(リオタールはジョン・ラングショー・オースティンの発話行為に関する理論を援用していた)。この問題を解決するために、リオタールはユルゲン・ハーバーマスのようなヒューマニズムの立場を擁護している新カント派の哲学者の思想に認められている普遍性やコンセンサスの前提を否定しており、先験的な形而上学における調和を追求することよりむしろ、言語ゲームにおいてプラグマティックな評価を受けるための試行錯誤や多様性を維持することを主張していた。
リチャード・ローティ(1931-2007)
『哲学と自然の鏡』を通じてリチャード・ローティは、現代の分析哲学が科学の方法論を誤用していることを指摘していた。さらにローティは、現象から認知者と観察者が独立していることや意識との関連で自然現象を認知することを前提にしていた表象主義における伝統的な認識論の視点を批判していた。プラグマティストの枠組みにおける反基礎付け主義や反本質主義の支持者のようにローティは、規約主義や相対主義におけるポストモダンを支持していたが、他方で社会自由主義に関する活動についてのポストモダンを批判していた。
ジャン・ボードリヤール(1929-2007)
シミュラクラ現象によれば、デジタル技術を通じてコミュニケーションや意味付けが行われている時代においては、記号の交換可能性によって現実が単純化されていた。ボードリヤールによれば、主体が(政治的、文学的、芸術的、個人的な)産物から切り離され、その産物が主体を支配しておらず固定的な背景も有していない状況が想定されていた。そのためそれらの産物は産業化された社会における無関心や消極性を誘因していた。またボードリヤールによれば、読者や視聴者に直接的に影響を与えることがない外観はその外観と外観の中身との違いを感じさせておらず、皮肉なことであるが、存在しているはずの人間がその姿を消し去っており、バーチャルな世界は外観のみによって構成されていた。
フレドリック・ジェイムソン(1934-)
ホイットニー美術館でのレクチャーを通じて、ポストモダニズムを歴史、知的なトレンド、社会現象として最初に理論的に展開し、後に『ポストモダニズム・オア・ザ・カルチュラル・ロジック・オブ・レイト・キャピタリズム』(1991年)を記していた。折衷主義を採用していたが、ジェイムソンは、時代区分が人文科学における批評の前提に影響を与えていることを検証していた。ジェイムソンはモダニティの文化的運動における原動力としてユートピアニズムの意義を示しており、ポストモダニティの分析においてモダニティの運動を否定することから生じる政治的・実存的不確かさを指摘していた。スーザン・ソンタグと同様に、ジェイムソンは20世紀における大陸ヨーロッパの左派の思想をアメリカの読者に紹介しており、特にフランクフルト学派、構造主義、ポスト構造主義に関連した人々の思想が顕著であった。したがってアングロアメリカのアカデミズムの言葉でそれらの思想を「解釈している」ジェイムソンの仕事はそれらの思想を批評することと同等の意義を有していた。
ダグラス・ケルナー(1943-)
ポストモダニズムから誕生したジャーナルである『アナリシス・オブ・ザ・ジャーニー』の中で、ケルナーは「近代の理論における前提や方法」を捨て去らなければならないと主張していた。ポストモダニズムの流儀で定義されたケルナーの用語は進歩、変革、調整を基盤としていた。ケルナーは現実の経験や事例を考慮した理論で用いられている語を幅広く分析していた。ケルナーはそれらの分析に科学技術社会論(STS)を用いており、STSがなければ理論が完成しないと主張していた。その議論の射程はポストモダニズムの範囲を超えており、STSを核にしたカルチュラル・スタディーズを通じて解釈されていた。そしてアメリカ同時多発テロ事件がケルナーの解釈に影響を与えていた。その影響は計画的な襲撃と世界貿易センターと呼ばれた「グローバリゼーションの象徴」の崩壊といった事実に依拠した多数の表象であった。そしてポストモダニズムに対する多くの適切な定義や懸念が彼の解釈を確かなものにしていた。またケルナーはアメリカ同時多発テロ事件の影響を理解する上での問題を検証し続けていた。ケルナーは他者には理解できるが当事者には理解できないアイロニーといったポストモダンの限定的な枠組みを通じてのみ同時多発テロ事件が理解されることが可能であるのか否かといった疑問を呈していた[28]。さらにケルナーはポストモダンと整合する記号論の考え方を展開させていた。同時多発テロ事件の影響やポストモダンを通じて解釈されたシンボルを参考にしながら、ケルナーは人がその人生やその1ページを理解するために用いる「記号論の体系」のように同時多発テロ事件を表現し続けていた。記号が人の文化を理解するために必要であるといったケルナーの考え方は多くの文化が実存の代わりに記号を用いていたことから引き出されていた。そしてケルナーは多くのポストモダニズムの研究者がその考えに囚われていることを認めていた。またケルナーはボードリヤールやマルクス主義の考え方の中に可能性を見出していた。そして同時にケルナーはマルクス主義の終焉やその意義が失われていたことを認めていた。
ケルナーが示していた結論は明白であり、それはどんな現実の経験や記号が既に知られている現実と重なるのかについて今日用いられているポストモダニズムが決定的に関与しているであろうといったことであった[29]。
4 脱構築
最もよく知られたポストモダニストによる考え方の1つに「脱構築」があり、それはジャック・デリダによって提唱された哲学のテーマであり、文芸批評であり、テクスト分析であった。「脱構築」によるアプローチは、前提、イデオロギー上の基盤、ハイアラーキーによって支配された価値観、枠組みの中にあるテクストに対する既存の解釈に疑念を呈する分析を含んでいた。脱構築によるアプローチは、著者の見解のようなテクストの前提から引き出される著者の文化、イデオロギー、道徳的姿勢や知識に依拠することなく緻密にテクストを読み込む方法論を採用していた。またデリダは「テクスト以外には何も存在していない」と述べていた[30]。デリダは言語による世界は脱構築されたテクストの基本原理(文法)から影響を受けていることを示唆していた。デリダの方法論は、与えられたテクストの意味に対してある側面では異なっているが別の側面では類似している解釈やテクストの意味に限定された二項対立が内包している問題を認識することを含んでいた。デリダの哲学は建築では脱構築主義と呼ばれており、建築物のデザインにおける破片のような形状、要素の歪みやアンバランスさによって特徴付けられていたポストモダンのムーブメントに影響を与えていた。そして『コーラ・ル・ワークス』といった建築家のピーター・アイゼンマンとの共同プロジェクトの後、デリダはこのムーブメントに関与することから遠ざかることになった[31]。
5 ポストモダニズムと構造主義
構造主義は1950年代のフランスの研究者によって展開された哲学的な潮流であり、部分的にはフランスの実存主義に由来していた。構造主義はモダニズムの表出としても認識されていた。「ポスト構造主義者」は構造主義の厳密な解釈や適用から離れた立場の思想家であった。多くのアメリカの研究者はポスト構造主義をより広範に捉えており、ポスト構造主義がよく定義されていないもののポストモダンの一部であると認識していたが、多くのポスト構造主義者はその認識は間違っていると主張していた。構造主義者と呼ばれている思想家の中には、人類学者であるクロード・レヴィ=ストロース、言語学者であるフェルディナン・ド・ソシュール、マルクス主義の哲学者であるルイ・アルチュセール、記号学者であるアルジルダス・グレマスが含まれていた。精神分析学者であるジャック・ラカンや文学者であるロラン・バルトの初期の著作も同様に構造主義に分類されることがあった。構造主義から始まりポスト構造主義者になった人々の中に、ミシェル・フーコー、ロラン・バルト、ジャン・ボードリヤール、ジル・ドゥルーズがおり、他のポスト構造主義者の中に、ジャック・デリダ、ピエール・ブルデュー、ジャン=フランソワ・リオタール、ジュリア・クリステヴァ、エレーヌ・シクスス、リュス・イリガライが含まれていた。彼らが影響を与えたアメリカの知識人の中に、ジュディス・バトラー、ジョン・フィスク、ロザリンド・クラウス、アヴィタル・ロネル、ヘイデン・ホワイトが含まれていた。
ポスト構造主義は、一般に共有された公理や方法論によって定義づけられるものではなく、日々の出来事から抽象的な理論に至るまで、ある文化の側面が他の側面をどのように決定づけているのかを示すことによって定められていた。ポスト構造主義の思想家は還元主義、随伴現象説、そして因果関係が階層構造を形成しているといった考え方を否定していた。構造主義者と同様に、ポスト構造主義者は、人々のアイデンティティ、価値観、経済状況が固有の特徴を形成していくことよりむしろお互いに影響を及ぼし合っているといった仮定を議論の出発点にしていた[32]。そしてフランスの構造主義者は相対主義や社会構築主義を提唱していることを自認していた。しかしそれにもかかわらずフランスの構造主義者は、どのように研究の対象が基本的な関係の集合として還元主義的に示されているのかを研究する傾向にあった(その例として『神話論理』におけるクロード・レヴィ=ストロースの神話変換の定式が挙げられる[33])。ポスト構造主義の思想家は物が最低限持っていなければならない性質と他の物に対する依存を区別する実存に対して疑念を呈していた。
5.1 ポスト構造主義
ポスト構造主義者は一般的に原始的な文化、言語、アリストテレスの心理学、観念論における「基本的な関係」の定式化を否定していた。またポスト構造主義の運動に関連していた思想家における別の共通点は、絶対主義や、原始的な文化、言語、心理の内部における作用以上に大きな影響を与えている官僚主義や工業化の進展に伴う構造的なバイアス[34]を内在させている構造主義者による科学的な主張に対する批判的な視点にあった。そのような現実は、価値観やパラダイムから独立して存在するシステムとして、構造主義者の方法論を通じて詳細に分析されておらず、原因と結果の相互作用として理解されていた[35]。したがって多くのポスト構造主義者は、システムの機能に対して構造主義者より幅広い解釈を採用しており、循環論法的な側面やあいまいな側面を時として批判していた。ポスト構造主義者は、それらを詳細に分析した上で、構造主義者による現象、現実、真実を示す主張が逆説的な循環論法による論証に依存していると反論していた。そして研究を通じて新たな視点が影響力をもち、その新たな理論が実現されていくことに見られる客観性の獲得のプロセスよりむしろ、その理論の中に登場する潜在的な循環論法やパラドックスのパターンを見出すことが重要であった。またある視点によれば、ポスト構造主義者はマルティン・ハイデッガーによる哲学の流れを組みながら、フリードリヒ・ニーチェの著作がもつ含意を敷衍していた。
ポスト構造主義者の著作は、経験、身体、社会、経済と知識との関係や知識に対する体系的な視点の中に多様な分野からの主張をまとめている傾向にあり、その体系的な視点に対してポスト構造主義の主張が関与しているとみなされていた。そして多少なりとも学際的な構造主義者は、学際性を主張しているにもかかわらず、専門分野の枠組みを好ましく考えており、研究対象を分析するためのアプローチに対して他分野からの視点を介在させない専門分野の独立性に固執する傾向にあった。構造主義者と異なりポスト構造主義者は、ある現象に対する「複数の関係」から成り立っているシステムを絶対視しておらず、独立した自己充足的な要素から成り立っている現実を反映したものというよりむしろある主張の狙いの帰結として「その関係」やシステムを認識する傾向にあった。どちらかと言えば一部の客観的な事実を取り上げてもそうであるが、ポスト構造主義の理論は社会秩序に関する統制における広範であいまいなパターンを示していたが、そのパターンを理論として無条件にまとめ上げることは不可能であった。このため一部のポスト構造主義者は反知性主義や反哲学を理由にしてリアリスト、自然主義者、本質主義者から批判されていた。構造主義者と比較してポスト構造主義者は、理論の前提が全体に対するバイアスや権力の影響から独立していることに対して懐疑的であり、社会に対する分析、記号論、哲学における推論において「純粋に理論的」で「科学的」なアプローチを否定する傾向にあった。ポスト構造主義者によれば、理論を通じて人間社会や心理学におけるいかなる現象も基本的なシステムや抽象化されたパターンに分解することは不可能であり、抽象化されたシステムを基本的な性質を保持した副産物として処理することも不可能であり、体系化された理論、現象、価値観がお互いの一部分を形成していた。
6 ポスト・ポストモダニズム
近年になってメタモダニズム、ポスト・ポストモダニズムや「ポストモダニズムの終焉」が幅広く論じられていた。2007年に「アフター・ポストモダニズム」と題されたザ・ジャーナル・トゥエンティース・センチュリー・リテラチャーの特別号のイントロダクションの中でアンドリュー・ホーボレックは「ポストモダニズムの終焉に言及することはありふれた批評の姿になっている」と述べていた。一部の評論家はポストモダニズムを通じて文化や社会を記述することを目的とした理論の限界を示しており、著名な研究者の中にラウル・エシェルマン(パフォーマティズム)、ジル・リポヴェツキー(ハイパーモダニティ)、ニコラ・ブリオー(アフターモダン)、アラン・カービィ(以前はスードモダニズムと呼ばれていたディジモダニズム)が含まれていた。これらの新しい理論や名称は今までのところ幅広く認められていた訳ではなかった。ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館で開催されていた「ポストモダニズムースタイルと破壊 1970-1990」(ロンドン、2011年9月24日-2012年1月15日)はポストモダニズムを歴史上の運動として記録した最初の展覧会であった。
http://en.wikipedia.org/wiki/Post-postmodernism
ポスト・ポストモダニズム
ポスト・ポストモダニズムは、批評理論、哲学、建築、芸術、文学、文化における幅広い展開を示しており、それはポストモダニズムの影響を受けており、ポストモダニズムから生じていた。そして他の類似の語はメタモダニズムであった。
1 歴史
多くの研究者は、モダニズムが19世紀後半に始まり、20世紀中頃まで西洋文化の知的サークルに文化的な影響を与え続けてきたことに対して意見が一致していた[1]。あらゆる節目を通じて明らかなように、モダニズムは多くの問題を含む視点を抱えており、統一された個々の集合として定義することが不可能であった。しかしその主な特徴は、人間関係における確からしさ、芸術の抽象化、理想主義の追求についての研究に見られるように、「ラディカルな美学、テクニカルな実験、時間軸よりむしろ空間軸、自意識の反映」[2]を強調していたと考えられていた。これらの特徴はポストモダニズムにおいて除外されており、アイロニーの対象として考えられていた。
ポストモダニズムは第二次世界大戦後に認識されていたモダニズムの失敗に対する反応から生じており、モダニズムの芸術におけるラディカルなプロジェクトが全体主義に結びつきながら主流の文化に融合されていったことが指摘されていた[3]。ポストモダニズムと呼ばれるものの萌芽は1940年代に散見されており、ホルヘ・ルイス・ボルヘスが有名であった[4]。しかし今日の多くの研究者は、1950年代後半にポストモダニズムがモダニズムと齟齬をきたし始めており、1960年代に優勢な地位を占めていったことに対して意見が一致していた[5]。その後ポストモダニズムは、異論があるものの、芸術、文学、映画、音楽、ドラマ、建築、哲学において支配的になっていった。ポストモダニズムの特徴は、スタイル、台詞の引用、語り方においてアイロニックな演劇[6]、西洋の文化のメタナラティブに対する懐疑主義やニヒリズム[7]、真実を犠牲にした現実の選択(正確に言えば「真実」は何によって成立しているのかといった根本的なことに対する問題意識)[8]、スキゾフレニアに類似した意識の状態を含むさまざまな現実の相互作用から影響を受けている[10]主体の局所的な「ウェイニング・オブ・アフェクト」[9]を含んでいると考えられていた。
そして1990年代後半以降の大衆文化やアカデミズムの世界においてポストモダニズムが「廃れてきている」との考えが広まり始めていた[11]。しかしポストモダニズムを継承する時代の名称や枠組みを定める取り組みはほとんどなく、提唱されていた名称も多数派からの支持を得ていなかった。
2 定義
何が時代を形成しているのかについてのコンセンサスが得られておらず、時代自体がまだ始まりの段階にあった。しかしながらポスト・ポストモダニズムの枠組みを定める取り組みにおける共通のテーマは、信頼、対話、成果、誠意がポストモダンのアイロニーを超越して機能することにあった。その深さ、焦点、範囲に違いがあるものの以下にその定義を時系列順に並べることにする。
1995年に都市計画家であるトム・ターナーは、ポスト・ポストモダンを都市計画に適用することについて本一冊分の主張を述べていた[12]。ターナーは「何でもあり」というポストモダンの立場を批判しており、「建造環境のエキスパートが推論に信頼を加えるポスト・ポストモダニズムの夜明けを目の当たりにしていた」ことを示唆していた[13]。特にターナーは都市計画において時間を超越した構造や形についてのパターンの活用を主張していた。そのようなパターンとしてターナーは、老荘思想に影響されたアメリカの建築家であるクリストファー・アレクサンダーによる作品、ゲシュタルト心理学、心理学者であるカール・ユングの思考の枠組みを引用していた。名称に関して、ターナーは「ポスト・ポストモダニズムを採用しながらも、さらに良い名称を求める」ことを促していた[14]。
ロシアのポストモダニズムに関する1999年の著作の中で、ロシア系アメリカ人であるミハイル・エプシュテインは、ポストモダニズムが「「ポストモダニティ」と呼ばれている大きな歴史の産物であった」と述べていた[15]。エプシュテインは、結局のところポストモダニストの美学はありきたりなものになり、アイロニーと異なる新たな詩歌のための基礎を固めるであろうと考え、そのことを「超」といった接頭語を用いて示していた。
「ポストモダニズム」に続く新たな時代を示す名称を考慮するときに、「超」といった接頭語が顕著になるだろうと考えられていた。20世紀の後半は「ポスト」といった語が顕著であり、そのことは「真実」や「客観性」、「精神」や「主観性」、「ユートピア」や「理想」、「原点」や「オリジナリティ」、「誠実」や「感傷」のようなモダニティにおける概念の崩壊を意味していた。そしてこれらの概念の全てが「超主観性」、「超理想主義」、「トランスオリジナリティ」、「超叙情性」、「トランスセンチメンタリティ」等といった形で現在再登場していた[16]。
例としてエプシュテインは現代のロシアの詩人であるティムール・キビーロフの作品を引用していた[17]。
「ポストミレニアリズム」という語は2000年にアメリカの人文系の研究者であるエリック・ガンズによって紹介されており[18]、倫理学や政治社会学におけるポストモダニズムに続く時代が示されていた。ガンズはアウシュビッツや広島の経験によって明らかになった加害者と被害者の倫理観の対立に基づく「被害者を過度に偏重した考え方」とポストモダニズムを密接に結びつけていた。ガンズの視点によれば、ポストモダニズムの倫理観は被害者の周辺に視点をおき、加害者側のユートピアを軽蔑することから生じていた。この意味におけるポストモダニズムは、近代のユートピアや全体主義に反対することについては有益であったが、和解のために長期的に役に立つ資本主義やリベラル・デモクラシーについて有益とならず被害者を過度に偏重した政治観によって特徴付けられていた。ポストモダニズムと比較して、ポストミレニアリズムは被害者を過度に偏重した立場をとらないことによって特徴付けられており、「被害者を過度に偏重しないダイアローグ」を採用していた[19]。ガンズはウェブ上のクロニクルズ・オブ・ラブ・アンド・リゼントメントを通じてポストミレニアリズムの考え方をさらに発展させており[21]、その語はジェネラティブ・アンソロポロジーに対する理論や歴史観と密接に結びついていた[22]。
2006年にイギリスの研究者であるアラン・カービィは「スードモダニズム」と呼ばれているポスト・ポストモダニズムに対して社会文化的な評価を行なっていた[23]。カービィはインターネットによって実現された文化の1つである世界一斉に表向き何かに直接関与する行為によって生じているうんざり感や中身の浅薄さとスードモダニズムとを関連付けており、「スードモダニズムの時代において、人々はスマートフォンを利用し、クリックし、文字を入力し、サイトを眺め、選択肢から何かを選び、サイトを移動し、ダウンロードするだけになってしまった」と述べていた[23]。
スードモダニズムにおける「典型的な知的状況」は「無知、熱狂、不安」として描かれており、実質を伴わず「超」の語がついただけの現状を生み出すだけであった。どうでもいいことに世界一斉に参加してメディアに簡単に煽られてしまう浅薄さによって生じた帰結は「モダニズム特有の強迫観念的な細かさやポストモダニズム特有のナルシシズム」と入れ替わった「有意義な情報や意思を伝えることも感情的な交流をすることもない状況」でしかなかった。カービィは美学的に価値のある結果が「スードモダニズム」から生じることはないと認識していた。スードモダニズムのくだらなさの例として、カービィはテレビ、双方向型ニュース、一部のウィキペディアでのデマ、ドキュソープ、マイケル・ムーアやモーガン・スパーロックの映画を引き合いに出していた[23]。2009年に出版された『ディジモダニズム:ハウ・ニュー・テクノロジーズ・ディスマントル・ザ・ポストモダン・アンド・リコンフィギュア・アワー・カルチャー』の中で、カービィはポストモダニズム後の文化に対する視点を仄めかしていた。
2010年にティモーテウス・バーミューレンとロビン・ファン・デン・アッカーはポスト・ポストモダニズムに関する議論を収斂させるためにメタモダニズムという語[24]を用いていた。『ノーツ・オン・メタモダニズム』という記事の中で、彼らは近代の視点とポストモダンの視点の間で揺れ動いている感性の登場によって2000年代が特徴付けられていると述べていた。メタモダンに影響された感性の例として、バーミューレンとファン・デン・アッカーは気候変動、金融危機、政情不安に対する反応によって示されている「多くの知識をもちながら知らないことも多い」、「プラグマティックな理想主義」、「節度を意識している熱狂」を引き合いに出していた。
美学的視点からメタモダニズムはヘルツォーク&ド・ムーロンによる建築、ミシェル・ゴンドリー、スパイク・ジョーンズ、ウェス・アンダーソンによる映画、ココロージー、アントニー・アンド・ザ・ジョンソンズ、ジョルジュ・レンツ、デヴェンドラ・バンハートによる音楽、ピーター・ドイグ、オラファー・エリアソン、ラグナル・キャルタンソン、セイラ・カメリッチ、ポーラ・ドープフナーによる作品、村上春樹、ロベルト・ボラーニョ、デヴィッド・フォスター・ウォレス、ジョナサン・フランゼンによる著作のように多様な芸術として示されており、絶え間ない想念の揺れ動きや近代とポストモダンに対する態度や考え方における真ん中の立ち位置によって特徴付けられており、それらのどれにも属さない感性を示唆しており、意味を求めながら意味を疑い、希望と悲嘆を抱え、誠意とアイロニーを同居させ、多くの知識を持ちながら知らないことも多く、構築と破壊を同時に行いながら、普遍的な真実の追求と相対主義の対立の克服を示していた[25]。
接頭語である「メタ」は思索的な立場ではなくプラトンが述べていた中間者に関係しており、議論の両端を揺れ動く態度を示していた[26]。
「一般的に「ポスト・ポストモダニズム」はポストモダニズムに対峙する概念と考えられていたが、ムハンマド・ジアウル・ハックは、ポスト・ポストモダニズムがポストモダニズムと対立する時代を示している訳ではなく、それがポストモダニズムの副産物であることを示しており、両者を区別するものは「想像力」にあった。言い換えるならばポスト・ポストモダニズムは、哲学、批評、構造デザイン、芸術、文化、文学におけるポストモダンの拡張を含んでおり、新機軸を打ち立てるために制度として確立された制約を打破することを目指していた[27]。
http://en.wikipedia.org/wiki/Metamodernism
メタモダニズム
メタモダニズムはポストモダニズムに対する反応として生じていた哲学、美学、文化の潮流の1つであった。ある定義によればメタモダニズムはモダニズムとポストモダニズムの対立を克服しており、メタモダニズムはポスト・ポストモダニズムに類似していた。
1 語の史的展開
メタモダニズムという語は1975年前後に登場しており、ザーヴァルザーダは1950年代中頃からアメリカ文学に生じているある種の美学や視点を示すためにその語を用いていた[1]。
1999年までにメタモダニズムは「モダニティやポストモダニティにおける妥当性を保ちながら、超越し、解体し、ひっくり返し、抜け道を探し、よく調査し、棚上げする」ための「モダニズムやポストモダニズムの拡張やそれらに対する疑念」として描かれていた[2]。そして2002年に文学のメタモダニズムは「モダニズムを通じた今後の...そして出発点として不滅の」美学として示されていた[3][4]。メタモダニズムとモダニズムの関係は「対立関係を超越しており、モダニズムの射程から外れた主体に焦点を当てるためにモダニストの方法論に再度対峙していく」ものとして示されていた[3]。
2007年の時点ではメタモダニズムはポストモダニズムと部分的に重なり合い、ある部分ではその派生であったが、別の部分ではポストモダニズムに対する反応として示されており、「相互の関連や永続的な変化といった枠組みの中でのみ現代文化や現代文学の特徴を理解することができるといった視点を肯定していた。」[5]
1.1 バーミューレンとファン・デン・アッカー
2010年にティモーテウス・バーミューレンとロビン・ファン・デン・アッカーはメタモダニズムをポスト・ポストモダニズムを巡る論争の行き着く場所として提案していた[6][7]。ノーツ・オン・メタモダニズムの中で彼らは1980年代や1990年代のポストモダンの視点を生かしながら典型的な近代へ回帰する姿勢によって2000年代が特徴付けられていたと論じていた。彼らによれば、メタモダニズムの感性は、気候変動、金融危機、政情不安、デジタル革命のような現在のグローバルな状況に対する文化的な反応の特徴である「ある面では多くの知識をもちながら知らないことも多く、プラグマティックな理想主義を示しているものとして考えられていた」[6]。彼らは「ポストモダン文化における相対主義、アイロニー、ゴチャ混ぜの文化」が終焉を迎えており、積極的に関与し、共感し、中身を伝えることに価値を認めるポスト・イデオロギーの状況が生じていると述べていた[8]。
「メタ」という接頭語は思索的な立場を示している訳ではなく、プラトンが述べていた中間者に関係しており、議論の両端を揺れ動く態度を示していた[6]。バーミューレンとファン・デン・アッカーはメタモダニズムを「多くの点の間を揺り動く振り子」のようにモダニズムとポストモダニズムの間を揺れ動く「心構えの構造」として示していた[9]。アートニュースの紙面におけるキム・レヴィンによれば、この揺れ動きは「期待と落胆、誠意とアイロニー、愛情と反感、個人的な問題と政治的な問題、技術的観点とマニアの視点に対して等しく懐疑的な心構えを示している」と思われていた[8]。メタモダニズムの時代を迎えて、バーミューレンは「かつてのメタナラティブが問題を抱えながらも必要とされており、理想がこれまでの歴史から信頼するに値しない幻滅の対象としてしか認識されない必然性はなく、愛情が馬鹿げた思い込みと必然的に同一である訳でもなかった」ことを示していた[10]。
バーミューレンは「メタモダニズムは枠組みの中の存在論を示唆している哲学と言うより、政治経済から芸術まで私たちの身の回りで何が起こっているのかを説明するオープンソースのドキュメントのような試みである」と述べていた[10]。ロマン主義の感性に回帰することがメタモダニズムの主な特徴であり、バーミューレンとファン・デン・アッカーによるヘルツォーク&ド・ムーロンの建築物や、バス・ヤン・アデル、ピーター・ドイグ、オラファー・エリアソン、ケイ・ドナチー、チャールズ・エイブリー、ラグナル・キャルタンソンのような芸術家の作品の中にメタモダニズムを認めることが可能であった[6]。
2 文化的な支持
2011年11月にニューヨークにあるミュージアム・オブ・アーツ・アンド・デザインはバーミューレンとファン・デン・アッカーによる影響を示しており、ピルヴィ・タカラ、グイド・ヴァン・デル・ワーブ、ベンジャミン・マーティン、マリーヒェン・ダンツの作品を扱った『ノー・モア・モダン:ノーツ・オン・メタモダニズム』といったタイトルの展覧会を開催していた[11]。
2012年3月にベルリンにあるギャラリー・ターニャ・ワーグナーはバーミューレンとファン・デン・アッカーと共同でディスカッシング・メタモダニズムを企画しており、メタモダニズムを扱ったヨーロッパで初めての展覧会を開催していた[12][13][14]。その展覧会は、ウルフ・アムアインド、ヤエル・バルタナ、モニカ・ボンヴィチーニ、マリーヒェン・ダンツ、アナベル・ダウ、ポーラ・ドープフナー、オラファー・エリアソン、モナ・ハトゥム、アンディ・ホールデン、セイラ・カメリッチ、ラグナル・キャルタンソン、クリス・レムサル、イッサ・サント、デビッド・ソープ、アンジェリカ・J・トロイナースキ、ルーク・ターナー、ナスティア・ロンッコの作品を扱っていた[14]。
映画を通じて「独特の」感性を表現することについて、研究者であるジェームズ・マクダウェルは、ウェス・アンダーソン、ミシェル・ゴンドリー、スパイク・ジョーンズ、ミランダ・ジュライ、チャーリー・カウフマンの作品を「新しい意味での誠意」をベースにしながら「アイロニーと誠意」のバランスを保っている心構えを表しているメタモダンの構造を具体化したものであると述べていた[9]。
アメリカン・ブック・レビューの2013年号はメタモダニズムを扱っており、ロベルト・ボラーニョ、デイヴ・エガーズ、ジョナサン・フランゼン、村上春樹、ザディー・スミス、デヴィッド・フォスター・ウォレスをメタモダニストとして認める一連のエッセイを含めていた[15][16]。PMLAの2014年の論文の中で、文学者であるデイビッド・ジェームズやウルミラ・セシャジリは「トム・マッカーシーのような21世紀の作家を論じながら、メタモダニストの著作が初期の文化的ムーブメントによる美学の遺産を取り入れながら適応しており、他方でその遺産に反応しながら問題を複雑にしている」と述べていた[17]。
大学の教員でありアートパルスで執筆しているスティーブン・クヌーセンは、メタモダニズムが「ばらばらな他のテクストとの関係からあらゆるものの意味を定めることに対するリオタールの苦悩やポスト構造主義者による主観性の脱構築に共感を寄せており、他方で本物の主張やクリエイターを積極的に擁護しており、モダニズムの美点に回帰していた」と記していた[18]。
2014年5月にカントリー・ミュージックのスターギル・シンプソンはカントリー・ミュージック・テレビジョンの中で『メタモダン・サウンズ・イン・カントリー・ミュージック』というアルバムがメタモダニズムについての記事をハフィントンポストで書いているセス・アブラムソンから部分的な影響を受けていると語っていた[19][20]。シンプソンは「技術の変遷が今まで以上に早くなっているにもかかわらず、アブラムソンはノスタルジーを感じさせるような環境で暮らしている」と述べていた[19]。J・T・ウェルシュによれば、「アブラムソンはこれまでの知的財産がモダニズムやポストモダニズムの影響によって分断されていた現状を超越する方法論として「メタ」という接頭語を理解していた」[21]。
2.1 メタモダニスト・マニフェスト
2011年にルーク・ターナーはメタモダニスト・マニフェストを発表していた[21]。マニフェストは「さまざまな主張の中での揺れ動きは当然のことである」と認識しており、その揺れ動きは「1世紀に及ぶモダニストの認識の甘さとアイロニーとの対立から生じていた惰性的な議論に」終焉を求めていた[21][22]。そして代わりにそのマニフェストは「ばらばらな複数の土台を求めることによって、誠意とアイロニーを同居させ、多くの知識をもちながら知らないことも多く、普遍性を否定しながら普遍性を求め、楽観的な態度を取りながら懐疑的な姿勢でもある揺れ動く心構え」としてのメタモダニズムを論じていた[23]。またそのマニフェストはバーミューレンとファン・デン・アッカーの作品を引き合いに出し、「私たちは開拓を継続し、揺れ動き続けなければならない」と締めくくっていた[24][10]。その後ターナーはマニフェストに対して俳優であるシャイア・ラブーフが芸術面で貢献していたことに言及していた[25][26]。
2014年の初めにシャイア・ラブーフはターナーやナスティア・ロンッコとの共同制作を始めており、デイズドによれば『名声や名誉の危うさを考察するためのプラットフォーム』と題されており、共同制作者によればメタモダニストによるパフォーマンスアートとして認識されていた[27]。これは『#アイ・アム・ソーリー』と題されていたロサンゼルス - ギャラリーでのパフォーマンスを含んでおり、ラブーフは6日間静かに座りながら観客の前で泣き続け、タキシードを着用しながら『私はもう有名人ではない』と記された茶色の紙袋を頭に被っていた[28]。
http://en.wikipedia.org/wiki/Remodernism
リモダニズム
リモダニズムは特に初期のモダニズムのある側面を取り上げており、ポストモダニズムに倣いながらもポストモダニズムを対比する視点を有していた。リモダニズムの支持者はリモダニズムが前衛的でラディカルな側面を有しているものの単なる反動ではないことを主張していた[1][2]。
2000年にスタッキズムと呼ばれるムーブメントの創始者であるビリー・チャイルディッシュとチャールズ・トムソンはリモダニズムを取り上げており、その声明によれば、シニカルで精神的に荒廃していたポストモダニズムに代わって、リモダニズムが芸術、文化、社会に新たな精神を取り込むための試みであることが述べられていた。2002年に開催されたリモダニズムの展覧会に向けてカリフォルニア大学バークレー校の教員であるケビン・ラドリーによるエッセイが寄せられており、アイロニーやシニシズムによる限界を超えた新たな芸術が存在しており、新たな美の感性が存在していることが示されていた。
2006年にアムステルダム市立美術館とアムステル大学はダニエル・バーンバウムやアリソン・ジンジェラスによるリモダニズムについての講演会を開催しており、その入門編としてメディアでの言説に対抗しながら、本物のよさ、積極的な自己表現、芸術の自己肯定のような伝統的なモダニストの価値観への回帰としての絵画のリバイバルについての講演を行なっていた[4]。2008年にロンドンイブニングスタンダードの評論家であるベン・ルイスは3つのターナー賞にリモダニズムを採用しており、20世紀初頭の形式主義のリバイバルとしてその3つのターナー賞を位置づけていた。ベン・ルイスは節度、寛大な態度、本物の感情に基づく美学といった価値観を支持していた[5]。
1 歴史
スタッキズムと呼ばれるムーブメントの創始者であるチャールズ・トムソンやビリー・チャイルディッシュはリモダニズムの時代を切り開いていた[3]。2000年3月1日にリモダニストによるマニフェストが公表されており、それは芸術の理想、本物のよさ、積極的な自己表現を肯定しており、絵画に力点を置きながらも「芸術に新たな精神を」取り込んでいた。その前提はモダニストによる理想がまだ十分に生かされていないことであり、その目標はその理想が誤用されている現状においてその役割を回復させ、再度定義させ、リバイバルさせることにあった。リモダニズムは真実、知識、その内容を肯定しており、形式主義に疑念を抱いていた。
そのイントロとして「ポストモダンの戯言によってモダニズムはその意味を見失っていた」といった言葉が紹介されていた。そしてニヒリズム、科学的唯物論、方向性の定まらない破壊に対抗して勇気、個性、一般性、コミュニケーション、人間性を強調した14の視点を示していた。その中の7番目の視点は次のようなものであった。
精神性の追求は魂の旅であり、最初にやるべきことは真実と向き合うために暗黙の意味を列挙することであった。真実は今実際に存在しているものであり、願望とは異なっていた。精神性を追求する芸術家であることは、善悪、美醜、迷いや自信をはっきりと述べることを意味しており、それは私たち自身と他者との関係さらに神との関係を知ることを含んでいた。
9番目の視点によれば、「精神性を追求する芸術は宗教と異なっており、精神性を追求することは自身を理解することや芸術家の明晰さや芸術の高い完成度を通じてその哲学を見出すことを念頭に置きながら人間性を追求することを意味していた。」 12番目の視点によれば、「神」という語の用法はギリシア語の「神によって所有された」を意味する「情熱」と結び付けられていた。
そのまとめとして、「きちんとした心がある人々にとって、支配階級であるエリートによって創作された芸術が明らかにしているように、現在発表されている芸術が理性による成果の失敗を示していることは明白であり」、その解決法は精神性を追求しているルネサンスにあり、「他に芸術が歩むべき道は存在しておらず、スタッキズムからの提案は精神性を追求するルネサンスを今すぐに始めることであった。」[6]
チャイルディッシュやトムソンはリモダニズムのマニフェストをニコラス・セロタ卿、テート・ギャラリーの理事に送っていたが、「あなた方は私があなた方の手紙やリモダニズムのマニフェストにコメントしないことを知っても特段驚くことはないでしょう」との返事があったのみであった[8][9]。
2000年3月にスタッキストは、『ザ・レジグネイション・オブ・サー・ニコラス・セロタ』と題した展示によって彼らがリモダニストによる初めての芸術グループであることを宣言していた。4月にリモダニズムは『ザ・ガルフ・ニューズ(UAE)』に引用されていた[10]。5月にオブザーバー紙はスタッキストによる展覧会を告知していた。「リモダニズムと呼ばれる芸術的ムーブメントに関わっているグループは明白な概念論に反対しており、形のある絵画を通じて感情や精神性の完成度を高めることを主張する展覧会のチケットの販売に経済面で依存していた。」[11]
6月にトムソンやチャイルディッシュはインスティチュート・オブ・アイデアズによって主催されたケンジントンにあるサロン・デ・ザールでスタッキズムやリモダニズムについての講演を行っていた[12]。同月に「スチューデンツ・フォー・スタッキズム」は「リモダニストによる講演会」を行なっていた。ザ・インスティチュート・オブ・リモダニズムはカテレ・アーマディによって設立されていた。
2001年にトムソンはイギリスの総選挙に立候補しており、「スタッキスト党は政治の場にスタッキズムやリモダニズムの考え方を導入する目的で結成された」と述べていた[13]。
2002年1月にマニフィコ・アーツはニューメキシコ大学の大学院生による「リモ:リモダニズム」[14]と題された展覧会を開催していた。芸術家による講演会の場で、カリフォルニア大学バークレー校の教員であるケビン・ラドリーは「リモダニズムは後向きではなく常に前を向いている」と述べていた[2]。展示会の寄稿文の中でラドリーは以下のように記していた。
...芸術家の主張に自信が取り戻されており、芸術家が皮肉、冷笑、教訓に煩わされることなく個性を追求することが可能であるといった視点が蘇っていた。その狙いは存在の意味を再び取り上げ、美の意味を練り直し、共感することの必要性を再度取り上げることにあった[15]。
展覧会のキュレーターであるヨシミ・ハヤシは次のように述べていた。
「リモ」はモダニズム、アバンギャルド、ポストモダニズム由来の考え方を混在させており、芸術に対するオルタナティブと主流派のアプローチを統合していた。「リモ」では多文化主義、アイロニー、高尚さ、アイデンティティに関する問題が取り扱われていたが、それのみで芸術を確立している訳ではなかった。伝統に対する再考と再定義は単なる脱構築によって成された訳ではなく、概念の接点を探しつなげることによって成されていた。定義によれば「リモ」は基本的に細胞に例えられており、そのルーツは芸術の周縁部分に由来していた[16]。
2003年に独立団体であるザ・スタッキスト・フォトグラファーズがアンディ・ブロックとラリー・ダンスタンによってリモダニズムに対する賛同を目的として設立されていた[17]。
2004年にアイルランドのクリエイター集団であるザ・デファスニスツはリモダニストのグループであることを宣言していた[18]。リモダニストの美術館であるザ・ディートリック・ギャラリーはケンタッキー州のルイビルに設立されていた。アメリカの映画製作者およびカメラマンであるジェシー・リチャーズとハリス・スミスはリモダニストの映画や写真についての新たなグループを共同設立しており、感情が意味するものを強調しており、ヌーベルバーグ、ノー・ウェーブ、表現主義、超越を映画製作の要素に組み込んでいた。
スタッキズムの芸術家であるビル・ルイスは2004年のリバプール・ビエンナーレでのBBCによるインタビューの中で、リモダニズムは「厳密な意味での芸術的ムーブメントではなく」、新たなパラダイムへ芸術を押し進めるためにモダニズムの原点に回帰することを意味していると述べていた[1]。リモダナイズすることは「再び原点に戻ること」であり、絵画から始まり...そして芸術がどこへ向かうのかを俯瞰することであった[1]。ビル・ルイスは、リモダナイズすることはポストモダンに対する自然な反応であると言われているが、「語の本当の意味においては」ラディカルな内容を指していると述べていた[1]。ニューヨークのスタッキズムの芸術家であるテリー・マークスは、リモダニズムを通じてモダニズムが良い方向へ向かうことになったのだが、そこから「純粋な理念」へ方向転換して未開拓のオルタナティブを目指すための原点に回帰する必要があり、「より多くの人々が享受でき、より具体的な創作を追求し、私たちをどこに導くのかを示すことがその目標に含まれている」と述べていた[19]。
2004年にルーク・ヘイトンはザ・フューチャー・マガジンの中で、「リモダニズムは私たちがその芸術に対して好みを述べることを許容しているのではないか」と述べていた[20]。フランツ・フェルディナンドのアレックス・カプラノスは「リモダニズムにとっても芸術家が魂を掲げることにとっても2004年が記念すべき年であった」と宣言していた[21]。
2005年8月に『アドレシング・ザ・シャドウ・アンド・メイキング・フレンズ・ウィズ・ワイルド・ドッグズ』と題された展覧会(スタッキストによるリモダニズムのマニフェストに由来している)がニューヨークのCBGBの313ギャラリーで開催されていた[22]。芸術家でありブロガーであるマーク・バレンは、「1970年代の半ばにパンクはCBGBと呼ばれていたニューヨークの湿っぽい場所にある小さなナイトクラブから生まれていた。そしてテレヴィジョン、ラモーンズ、パティ・スミスのようなロッカー達が商業ロックの流れに対して正面攻撃を加えていたときに、すべてが始まっていた。現在、音楽における第二の抵抗運動としてリモダニズムがパンクの聖地から商業ロックの流れに対して攻撃を加えようとしている」と述べていた[22]。
2006年5月10日にアムステル大学市立近代美術館とアムステル大学はアートフォーラムの編集者であるダニエル・バーンバウムやグッゲンハイム美術館のアシスタント・キュレーターであるアリソン・ジンジェラスによるリモダニズムについての講演会を行なっていた[4]。その要旨は次のように示される。
近年私たちは絵画に対する関心がこれまでとは別の形で再度高まっているのを目の当たりにしており、私たちは芸術の自己肯定、本物のよさ、積極的な自己表現のような伝統的なモダニストの価値観に回帰する古代からの営みのリバイバルを経験しているのであろうか。仮に私たちがモダニズム(リモダニズム)への回帰を話題にできるなら、これは芸術における立ち位置が真ん中にある学際的な試みをどこへ向かわせるのであろうか[4]。
2006年8月に「ザ・リモダニスツ・オブ・デヴィアントアート」と呼ばれるインターネット上のグループがクレイ・マーティンによって設立されていた。このグループはデヴィアントアート・ドットコムで活動する芸術家によって構成されていた。
2006年に芸術家であるマット・ブレイは「俺はスタッキストであるとは思われたくなく、たぶんいてもいなくても構わないピエロのような存在だろう。ザ・スタッキストは一番名の通ったリモダニストのグループだし、そのマニフェストに心が惹かれている。そして彼らには感謝している」と述べていた[23]。2007年5月にマット・ブレイはパンクのアダム・ブレイと一緒にイギリスのフォークストンでザ・マッド・モンク・コレクティブを立ち上げており、リモダニズムを広めていた[24]。
2008年1月にイブニングスタンダード紙の評論家であるベン・ルイスは、2008年が「モダニストのリバイバルを表現するための新たな語である『リモダニズム』」を経験する年になるだろうと述べており[25]、マーク・レッキー、ルナ・イスラム、ゴシュカ・マキュガを「20世紀初頭の形式主義のリバイバル」としてターナー賞にノミネートしており、「心が感じられるささやかで寛大な美学であること」を理由にしてマキュガを賞賛しており、それこそが今日必要とされていると述べていた[5]。2009年4月にベン・ルイスは「ノスタルジックな」16mmフィルムを用いるルーマニアの芸術家であるカタリナ・ニクレスクをモダニズムの余韻を嗜好する芸術の大きな流れの中に位置付けており「それをリモダニズムと呼ぼう」と述べていた[26]。
2008年8月27日にジェシー・リチャーズはリモダニスト・フィルム・マニフェストを発表しており、そのマニフェストは「映画における新たな精神性」を追求しており、映画製作に直感を導入しており、リモダニストによる映画を「むき出しで、必要最小限で、叙情的で、パンクの要素を含む映画製作である」と表現していた。そしてそのマニフェストはデジタル映像を用いた映画製作者であるスタンリー・キューブリックやドグマ95を批判していた。4番目の視点は次のようなものであった。
日本の意識の1つである侘・寂(不完全さを活かした美)や物の哀れ(移り行く物に対する感慨・過ぎ行く物に対するほろ苦い感情)は存在の真実を示すことの可能性を有しており、そのことはリモダニストによる映画が制作されるときにに常に念頭に置かれていた[27]。
その後の2009年にマングビーイング誌におけるリモダニストによる映画についてのエッセイの中で、リチャーズはプロと関連させながらリモダニズムを論じていた。
一般的にリモダニズムはアマチュアによる挑戦を肯定しており、プロを考察の対象として特殊な立場に置いていた。つまりこれまでのプロは失敗をなくすために励む存在であり、それゆえ「プロフェッショナル」であったが、私はそうは考えていない。そして仮にプロが絶えず成長する可能性を有する存在であるのならば、私はそのプロを支持したい。絵を描き、演技をし(内向的であるならば特に)、他の芸術家のためのモデルになり、宗教の仲立ちをし、意識のレベルに影響することを行い、他者を不快にさせることに対しても一歩足を踏み出し、外の世界での生活に触れ合い、見知らぬ大海に飛び込むことを実際に自分でやる映画製作者を支持したい。私はそれらがプロにとっての挑戦だろうと考えている[28]。
2009年にニック・クリストスとフロリダ・アトランティック大学の学生がマイアミ・スタッキスト・グループを設立していた。クリストスは「スタッキズムはモダニズムのルネサンスであり、リモダニズムである」と述べていた[29]。
7 批判
ポストモダニズムに対する批判は多様であり、ポストモダニズムが無意味であり、蒙昧主義にすぎないとの主張を包含していた。例えばノーム・チョムスキーは分析や経験を通じた知識に貢献していないことを理由にしてポストモダニズムが無意味であると主張していた。チョムスキーは、「理論の原理は何か、どの事実に基づいているのか、何が明らかにされていないのか...」と尋ねられたときに、なぜポストモダニストの知識人は他分野の研究者のように答えようとしないのかと尋ねていた。「仮にその答えがないのであれば、私は「情熱に対する」類似の状況におけるヒュームからのアドバイスを送りたい」[36]。キリスト教徒の哲学者であるウィリアム・レーン・クレイグは「私たちがポストモダンの文化の中で暮らしているというアイデアは幻想である。実際ポストモダンの文化はあり得ないものであった。そして人々に馴染まれるものではなかった。また科学、工学、技術の問題になると人々は相対主義の立場ではなかった。むしろ宗教や倫理の問題になったときに相対主義の立場を採用していた。そしてこの話から導き出されることはこのような立場はポストモダニズムではなくモダニズムであるということだ」と述べていた[37]。
ポストモダニズムに対する表立ったアカデミズムからの批判は例えば『ビヨンド・ザ・ホウクス・アンド・ファッショナブル・ナンセンス』のような作品の中に確認されている。
そしてアメリカのアカデミズムは大陸の哲学、特にフレンチ・セオリーを採用している研究者に対して「ポストモダニスト」のレッテルを貼る傾向にあった。そのような傾向はアメリカの比較文学部に由来しているかもしれなかった[38]。構造主義者やポストモダニストの世界観が同時に心理、社会、環境の領域を十分に説明できるほど融通がきくものではないと主張することによって「ポストモダニスト」と考えられていたフェリックス・ガタリがその理論の前提を否定していたことは興味深いことであった[39]。
http://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_postmodernism
ポストモダニズムに対する批判
ポストモダニズムに対する批判は多様であり、ポストモダニズムに意味がなく、蒙昧主義を後押ししているに過ぎないとの考えを含めていた。
1 あいまいさ
哲学者であるノーム・チョムスキーはポストモダニズムが分析や経験を通じた知識に貢献していないことを理由にして意味がないと主張していた。チョムスキーはなぜポストモダニストである知識人が他分野の研究者のように問いに答えようとしないのかと尋ねていた。
その問いとは、理論の原理は何か、どの事実に基づいているのか、何が明らかにされていないのかといったことであり、これらの問いは誰が投げ掛けても正当なものであった。仮にその答えがないのであれば、私は「情熱に対する」類似の状況におけるヒュームからのアドバイスを送りたい[2]。
類似の立場から、リチャード・ドーキンスはアラン・ソーカルとジャン・ブリクモンによる『「知」の欺瞞』を肯定的に評価していた[3]。
あなたが主張することがないにもかかわらず、アカデミズムの世界で成功し、弟子を集め、あなたの記述に対して世界中の学生から黄色の蛍光ペンでアンダーラインを引いてもらいたいと願う知的欺瞞を抱えているとしよう。あなたはどんな種類の文学のスタイルを確立しようとするだろうか。もちろん明快な答えがないことはあなたに中身がないことを示すことになろう。
ドーキンスはフェリックス・ガタリからの引用を「中身がないこと」の例として用いていた。
「ポストモダニズム」という用語が無意味なバズワードでしかないことが示唆されていた。例えば、ディック・ヘブディジは『ハイディング・イン・ザ・ライト』の中で次のように記していた。
人々が「ポストモダン」の枠組みの中に、インテリア、建物のデザイン、映画における物語空間、作品の構成や「スクラッチ」ビデオ、テレビコマーシャルや芸術のドキュメンタリー、間テクスト性、ファッション誌や批評誌におけるページのレイアウト、認識論における反目的論、「存在に対する形而上学」への批評、感情の意味を弱めること、中年の幻滅に対抗しようとするベビーブーマーである戦後世代の失意や不健全さ、反動の中の「苦境」、ひとまとまりの比喩、上辺だけの表現や関係の増加、日用品に対する愛着に対する新たな局面、イメージ、内輪の習わし、スタイルに魅了されること、文化・政治・存在の細分化、主体を「話題から外すこと」、「メタナラティブに対する警戒」、力の複数性によって一元的な力を置き換えること、「意味の内面を解体すること」、文化的なハイアラーキーの崩壊、個の自滅の脅威に対する不安、大学の没落、新たに細分化されたテクノロジーの影響、メディア・消費者・多国籍を包含する局面への社会経済のシフト、「場に囚われない」感覚や「場に囚われない」意識の放棄、一時的な座標空間に対する代替物を含めるならば、私たちがバズワードに囲まれていることは明白であった[4]。
例えばイギリスの歴史家であるペリー・アンダーソンのような人々は、「ポストモダニズム」という語が有しているさまざまな意味が互いに矛盾し合っており、ポストモダニストを分析することが現代文化に対する洞察をもたらすだろうと述べていた[5]。またカヤ・イルマズはポストモダニズムという語の定義が明確でなく筋が通っていないことを示していた。イルマズによれば、理論自体が反基礎付け主義であるためにポストモダニズムという語が基礎を有していないことが指摘されていた[6]。
2 道徳的相対主義
ある評論家はポストモダン社会が道徳的相対主義の言い換えであり、行動の逸脱を促していると解釈していた[7][8][9]。右派の作家であるチャールズ・コルソンは道徳的相対主義や状況倫理にあふれる不可知論と同様に不信の目でポストモダニズムの時代を眺めていた[10]。ジョシュ・マクドウェルとボブ・ホステトラーはポストモダニズムに対して次のような定義を与えており、「客観的な意味において真実は存在しておらず発見されるのではなくでっち上げられるといった信念に基づいた世界観」があり、真実は「一部の文化によってでっち上げられ、その文化でしか通用しなかった。そのため真実を語ろうとすることは力技であり、他の文化を支配する試みでもあった。」[11]
多くの哲学的ムーブメントは存在の健全な説明としてのモダニティやポストモダニティを否定していた。その一部は文化的ないし宗教的右派と関連しており、その右派はポストモダニティが基礎となる精神ないし当然の真実を否定しており物質的な満足を強調しながら内なるバランスや精神性を否定してきたと認識していた。これらの多くは、受け入れがたいポストモダンの条件[12]である「客観的な真実を放棄する」傾向を批判しており、真実を与えるメタナラティブを示すことを意図する傾向にあった。
3 マルクス主義による批判
カリニコスはボードリヤールやリオタールのようなポストモダンの思想家を批判しており、ポストモダニズムが「1968年5月の失望に終わった革命世代が「新たな中産階級」を形成していることを反映しており、知的ないし文化的な現象よりむしろ政治的なフラストレーションや社会的流動性の低下の兆しとして解釈されることが妥当である」と論じていた[13]。
美術史家であり社会主義労働者党のメンバーであるジョン・モリニューは「ブルジョア歴史家による古くからの主張の繰り返し」であることを理由にしてポストモダニストを批判していた[14]。
アメリカ文学の評論家でありマルクス主義者であるフレドリック・ジェイムソンはポストモダニズムを批判しており、資本主義やグローバル化の進展を支えるメタナラティブに関与することを否定しており、ポストモダニズムが「文化における後期資本主義のようなもの」であると主張していた。そしてポストモダニズムが支配と搾取につながっていると主張していた[15]。
ザ・アメリカン・インターナショナル・ソーシャリスト・オーガニゼーションのメンバーであるシェリー・ウルフは2009年の『セクシュアリティ・アンド・ソーシャリズム』の中でゲイ解放のための手段としてのポストモダニズムを否定していた[16]。
4 アート・バラックス
アート・バラックスは1999年4月のアート・レビューにおけるブライアン・アシュビーによる記事であった[17]。アシュビーは「ポストモダン」芸術における言語の意義を指摘していた[17]。アシュビーによるポストモダン芸術は「インスタレーション、写真、コンセプチュアル・アート、映像」の形式を採用していた。タイトルに含まれるバラックスはナンセンスに関連していた。
5 ソーカル事件
ニューヨーク大学の物理学教員であるアラン・ソーカルは事件を引き起こしており、ポストモダニストによる論文に類似したスタイルで意図的にナンセンスな論文を投稿していた。その論文は『ソーシャル・テキスト』誌によって受理され掲載されていた。
http://en.wikipedia.org/wiki/Postmodernity
ポストモダニティ
ポストモダニティは一般に経済や文化の姿やモダニティの後に存在している社会状況を説明するために用いられてきた。ある学派は20世紀後半の80年代から90年代初頭にかけてモダニティが終焉を迎えポストモダニティに移行したと主張していたが、他の学派はモダニティがポストモダニティによる展開を包含していると述べ、さらに他の学派はモダニティが第二次世界大戦によって終焉を迎えていたと主張していた。ポストモダンの条件はモダニズムの精神に反して自律的に機能する能力を奪う文化として特徴付けられていた[1]。
ポストモダニティはポストモダン社会つまりポストモダンを生み出している社会状況やポストモダン社会と関連している存在の現れ方に対する個々の反応を示していた。多くのコンテクストにおいて、ポストモダニティはポストモダニズム、芸術、文学、文化、社会におけるポストモダンの特徴と区別されていた。
1 語の用法
ポストモダニティはポストモダンを生み出す社会状況や条件であり、ポストモダン芸術ではモダンに対する反応であった。モダニティは進歩主義時代、産業革命、啓蒙時代と重なる時代として定義されていた。哲学や批評においてポストモダニティはモダニティの後に存在している社会状況やモダニティの終焉の要因となる歴史的状況を示していた。この用法は哲学者であるジャン・フランソワ・リオタールやジャン・ボードリヤールに由来していた。
ハーバーマスによれば、近代の「プロジェクト」は社会活動や芸術活動に合理性やハイアラーキーを導入することによって進歩を促していた(ポスト工業化、情報化時代を参照せよ)。リオタールは進歩の追求による確かな変化によって特徴付けられた文化の姿としてモダニティを位置づけていた。ポストモダニティは確かな変化が現れており進歩の概念が廃れきった状況を示していた。ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインによる絶対的な知の可能性に対する批判によれば、リオタールは実証主義、マルクス主義、構造主義のようなメタナラティブが進歩のための方法論として機能していないことを論じていた。
文学研究者であるフレドリック・ジェイムソンや地理学者であるデヴィッド・ハーヴェイはポストモダニティを「後期資本主義」や「フレキシブルな資本蓄積」、金融資本主義以降のヒトやモノが自由に移動する資本主義、ハーヴェイが「時間と空間の凝縮」と呼んでいるものと同一視していた。彼らはポストモダニティが第二次世界大戦以降の経済秩序とされるブレトンウッズ体制の崩壊と重なっていることを示唆していた(消費主義や批評理論を参照せよ)。
アウシュビッツや広島のような惨事を導いたヒューマニティの欠陥を取り上げてモダニティが完全な失敗であったと捉えている人々はポストモダニティをあるべき姿であると認識していた。近代のプロジェクトに自身を含めている多くの哲学者はポストモダニズムの帰結を示唆するためにポストモダニティを用いていた。ユルゲン・ハーバーマスを含む多くの研究者は近代のプロジェクトが未完に終わり普遍性が不要とされる反啓蒙主義の現れとしてポストモダニティを認識していた。このコンテクストでポストモダンの思想の帰結であるポストモダニティはネガティブな用語として用いられていた。
2 ポストモダニズム
ポストモダニティは制度や作品の変化(ギデンズ、1990年)やグローバルな視点を通じて特に1950年代の欧米における社会経済の推移に関連した状況を示しており、ポストモダニズムは美学、文学、政治哲学、社会哲学、特に1920年代の新たな芸術的ムーブメント以降の「文化的ないし知的現象」を含んでいた。ポストモダニティやポストモダニズムといった語は哲学者、社会科学者、そして現代文化、経済学、20世紀後半から21世紀初頭の生活を反映した社会の側面を批評する評論家によって用いられており、権威の分断化や知識の商品化を含んでいた(モダニティを参照せよ)。
そしてポストモダニティと批評理論、社会学と哲学の関係が問題になっていた。「ポストモダニティ」や「ポストモダニズム」といった語を区別することは難しく、ポストモダニティはポストモダニズムの帰結であった。そのプロセスは多様な政治的影響を内包しており、「反イデオロギー」がフェミニスト運動、人種差別撤廃運動、ゲイ・ライツ・ムーブメント、20世紀後半の多くのアナーキズム、平和運動、反グローバリゼーション運動とのハイブリッドと関連していた。これらの運動はポストモダンのムーブメントを肯定していなかったけれども、コアとなるアイデアのいくつかをポストモダンのムーブメントから借用していた。
3 歴史
リオタールやボードリヤールのような研究者はモダニティが20世紀後半に終焉を迎えていたと想定し、モダニティ以後をポストモダニティとして定義していたが、バウマンやギデンズのような研究者はモダニティの意味を拡張しながら、ポストモダニティによって示されているその後の展開を解釈していた。他の研究者はモダニティが1900年代のビクトリア朝時代に終焉を迎えていたと述べていた[2]。
ポストモダニティは1940年代後半や1950年代の初期から冷戦の終結にかけての段階(限られた帯域のアナログメディアが少数のメディアとして権威を維持していた時代であった)や冷戦の終結以降の段階(ケーブルテレビやデジタル時代の「新たなメディア」の普及によって特徴付けられた時代)といった2つの局面を通じて説明されていた。
ポストモダニティの最初の段階はモダニティの終焉と重なり、近代の一部として認識されていた(分類学や時代区分を参照せよ)。テレビが主なニュースの情報源になり、製造業が欧米の経済におけるその意義を低下させ、貿易が話題の中心を占めつつあった。1967年から1969年の先進国において文化が急速に発展し、それは社会の中でポストモダニティを経験しながら成長したベビーブーマーが政治、文化、教育の権力構造に参加することを求め始めていた時期でもあった。非暴力や文化的な活動からテロまでを含んでいるデモや抵抗運動は前の世代による政治や議論の設定に対する若い世代の異議申立てを示していた。アルジェリア戦争やベトナム戦争、人種差別を容認する法律、女性差別を助長する法律、離婚の制限に対する抵抗、マリファナや麻薬の使用の増加、ロックを含む音楽やドラマにおけるポップカルチャー、オーディオ・テレビ・ラジオの普及が幅広い文化のコンテクストの中で顕在化していた。60年代後半から70年代初頭の特徴は、メディア文化に囲まれた生活の帰結に注目しながら、マスメディア文化に参加することが社会規範の権威を揺るがすことを通じて自由をもたらしていたと述べていた哲学者であるマーシャル・マクルーハンの著作の中に示されていた。
ポストモダニティの次の段階は「デジタル化」によって特徴付けられており、ファックス、モデム、ケーブル、高速回線のインターネットといったコミュニケーションの手段がパーソナル化やデジタル化の影響力を増大させ、ポストモダニティの状況を劇的に変化させており、デジタル情報を通じて個人の力がこれまでメディアが有していたあらゆる側面に対して現実の力として作用していた。このことは知的財産権を巡る製作者と消費者の衝突を促しており、ニューエコノミーの支持者は情報コストの激しい低下が社会を根本的に変化させるだろうと述べていた。
そしてデジタル化ないしエスター・ダイソンによるデジタル化がポストモダニティと異なる状況として登場してきたことが指摘されていた。この立場の論者は、ポピュラー・カルチャーのアイテム、ウェブ、知識をインデックス化している検索エンジンの活用やテレコミュニケーション可能な力がヘンリー・ジェンキンスによる「参加型文化」の登場やAppleのiPodのようなデバイスの普及を通じた「過度の一極集中」を生み出していると論じていた。
この時代におけるシンプルではっきりとした境界線は1991年のソ連崩壊や中国の自由化であった。1989年にフランシス・フクヤマはベルリンの壁の崩壊を予想させる『歴史の終焉』を発表していた。フランシス・フクヤマによれば、政治哲学の問題は解決されており、価値観を巡る大規模な戦争はもはやあり得ないものであり、その理由として「あらゆる対立が解消され、あらゆる人間が円満な状況を必要としていること」が挙げられていた。そしてこれはある種の「エンディズム」であり、1984年にアーサー・ダントーはアンディ・ウォーホルによるブリロ・ボックスが形式主義を否定して芸術が終焉を迎えたことを歓迎していた。
4 論評
4.1 哲学と批評理論の区別
ポストモダニティに対する論争にはよく混同される2つの要素が存在していた。(1)現代社会の特徴と(2)現代社会に対する評論の特徴であった。前者は20世紀後半に端を発した変化の特徴であった。そして3つの代表的な分析が存在していた。カリニコス(1991年)やカルフーン(1995年)のような研究者は現代社会の特徴に対して保守的な立場を示しており、社会経済的変化の意義や程度を軽視しており、過去との連続性を強調していた。次にある領域の研究者は「近代」のプロジェクトが依然として「モダニティ」の段階のままである現在を分析しようとしていた。この意味での現在はウルリッヒ・ベックによれば「第二の」ないし「リスク」社会と呼ばれ(1986年)、ギデンズによれば「後期の」ないし「高度な」モダニティとして示されており(1990年・1991年)、ジグムント・バウマンによれば「リキッド」モダニティであり(2000年)、カステルによれば「ネットワーク」社会であった(1996年・1997年)。さらに別の研究者は現代社会がモダニティと異なるポストモダンの段階に移行していると論じていた。この立場を採用している研究者はリオタールやボードリヤールであった。
別の問題は評論の特徴に起因しており、モダニズムが普遍主義を示しておりポストモダニズムが相対主義を示していることを前提にしていたために、その普遍主義と相対主義の間における論争がしばしば生じていた。セイラ・ベンハビブ(1995年)やジュディス・バトラー(1995年)はこの論争をフェミニスト政治学と関連させ、ベンハビブはポストモダン批評が3つの要素から構成されていると論じており、主体やアイデンティティに対する反基礎付け主義者の考え方、目的論や社会の進歩といった概念や歴史の終焉、客観的な真理を求める形而上学の終焉を挙げていた。ベンハビブはこれらの視点に反論しており、これらの視点がフェミニスト政治学の基盤を損なっており、保護団体の可能性、自己の意味、解放の名の下に女性史が簒奪されてきたことを考慮していないと主張していた。規範としての理想の否定はユートピアの可能性、倫理の中心、民主主義に根差した活動を否定することにつながっていた。
バトラーはベンハビブに対してポストモダニズムという語の用法が反基礎付け主義やポスト構造主義を超えた妄想を含んでいると述べていた。
そして多くの視点がポストモダニズムに依拠していた。ディスコースが全てであり、ディスコースが全てを構成しているある種の一元論であるかのようであった。主体が喪失され、私が「私」に言及することができなかった。現実は存在しておらず、表象のみが存在していた。これらの論拠はポストモダニズムやポスト構造主義にあり、互いに関連し合い、脱構築とも関連し、フランスのフェミニズム、脱構築、ラカンの精神分析、フーコディアンの分析、ローティの対話主義、カルチュラル・スタディーズとして認識されていた。実際にはこれらのムーブメントは矛盾し合っていた。フランスにおけるラカンの精神分析はポスト構造主義と対立しており、フーコディアンはデリディアンとほとんど関連しておらず...リオタールはポストモダニズムという語を擁護していたが、それはその他大勢の自称ポストモダニストが行なっていることと異なっていた。またリオタールの研究はデリダのそれと異なっていた。
バトラーは、一方でどのように哲学が権力関係に関与しているのかを示しており、他方で問いの始まりが「普遍性」や「客観性」を疑うことであることを理由にして主体に対する批評が話の始まりであって終わりではないと述べているポスト構造主義者を支持しているポストモダニストによる批評の特徴を論争の対象にしていた。
ベンハビブとバトラーの論争はポストモダニティの定義自体が議論の対象であることから示されるようにポストモダニストに対する単純な定義が存在していないことを示していた。ミシェル・フーコーはインタビューの中でポストモダニズムのレッテルを貼られることを拒否していたが、ベンハビブを含む多くの人々は、啓蒙運動における普遍的な規範に疑念を呈することによってユートピアを示している「近代」の評論を否定していることを理由にしてフーコーが「ポストモダン」の評論を支持していると考えていた。ギデンズ(1990年)はこのように定義された「近代の」評論の特徴を認めておらず、啓蒙時代の普遍性に対する評論が近代の哲学者とりわけニーチェにとって主要な問題であったことを指摘していた。
4.2 ポストモダン社会
ジェイムソンはポストモダニティとモダニティの違いを示唆している多くの現象を認識していた。ジェイムソンは「新たなタイプの浅薄さ」や「深みのなさ」について言及しており、(解釈学、論理学、フロイトの抑圧、本物と偽物に対する実存主義者による区別、シニフィアンとシニフィエに対する記号論による区別において)「内側」と「外側」の視点を通じて人々や物事を説明しているモデルを否定していた。
そしてモダニストの「ユートピアに対する姿勢」やファン・ゴッホにおいてそうであるが芸術において苦悩を美に昇華することが否定されており、他方でポストモダニズムのムーブメントを通じて物質世界が「根本的な変化」を経験しており、「テキストや見てくれのごった煮になって」しまっていた(ジェイムソン、1993年)。モダンアートが世界を取り戻し、それを理想に据えて、魂をもたらすことを希求する一方で(グラフによれば、科学や宗教の没落が世界における価値を退廃させていた)、ポストモダンアートは世界に破滅を与えており、ポストモダンの破滅は、趣旨としては破滅と無関係であるのだが、見る側の視点を崩壊させていた。グラフは科学や合理主義の登場によって損なわれていた意味を与えるために宗教の代わりにアートを用いることの中にアート特有の変化を訴求するミッションを位置付けていたが、他方でポストモダンにおけるアートの役割が不毛であると認識していた。
さらにジェイムソンはポストモダンの特徴を「ウェイニング・オブ・アフェクト」として示しており、あらゆる感情がポストモダンが支配する時代から失われている訳ではなく、ポストモダンの時代がある特定の感情を失っていることを示しており、それは例えば「(あなたの方に振り向いてくれる)ランボーのマジカル・フラワーズ」のようなものであった。ジェイムソンは「その人の流儀が通用しない」「ごった煮となった権威の没落におけるパロディ」がそのごった煮に普遍性を与えていることを示唆していた。
ジェイムソンによれば、ポストモダニティにおいて物事の尺度が「喪失されて」おり、私たちが「ポストモダンの主体が我を見失ってしまうほどの多くの事柄の中に埋没してしまっている」ことが指摘されていた。この「新たなグローバル空間」はポストモダニティの「正念場」でもあった。ジェイムソンが認識しているポストモダンの他の特徴は「グローバル空間における存在のある側面として示されていた」。またポストモダンの時代は文化の社会的機能を変化させていた。ジェイムソンによれば、近代の文化は「中途半端に自律的」で、「現実を超えた存在」を仮定していたが、ポストモダンの文化はその自律性を奪っており、文化人の営みが社会全体を消費するまでに拡大しており、あらゆる人々が「文化人」になっていたことが指摘されていた。そして「評論における物事の尺度」であり左派の理論が依拠している「巨大な資本という存在」の蚊帳の外に文化が位置しているといった仮定は時代遅れになっていた。また多国籍資本の驚異的な拡大が資本主義に染まっていない地域(自然であれ意識であれ)を植民地化し尽くしてしまい、植民化される側は評論家にとって都合がよい状況を与えていた(ジェイムソン、1993年、54)。
4.3 社会科学
ポストモダン社会学は20世紀後半の先進国の生活に着目しており、マスメディアと大量生産・大量消費、グローバル・エコノミーの登場、製造業からサービス業へのシフトを視野に収めていた。ジェイムソンやハーヴェイはその生活を消費主義として描いており、製造、流通、その結果としての幅広い普及に要するコストは安価になっていたが、社会におけるつながりやコミュニティは一層希薄になっていた。他の思想家によれば、ポストモダニティは大量生産・ポピュリズムを前提とした社会におけるマスメディアに対する当然の反応であることが指摘されていた。アラスデア・マッキンタイアの著作はマーフィー(2003年)やビールスキス(2005年)のような著者によるポストモダニズムを紹介しており、マーフィーやビールスキスにとってアリストテレスの哲学に対するマッキンタイアによるポストモダン流の解釈は資本蓄積を加速させているある種の消費主義に対する抵抗として映っていた。
ポストモダニティに対する社会学的な視点は迅速な移動手段、コミュニケーションの範囲の拡大、断念せざるを得なかった大量生産のための標準化に原因を求めており、それらは以前より幅広い資本に価値を置き、その価値が多様な形で蓄積されることを許容するシステムを生み出していた。ハーヴェイによれば、ポストモダニティは「フォーディズム」からの脱却であり、それはアントニオ・グラムシによる造語であるが、1930年代初頭から1970年代までのOECD諸国においてケインズ政策を採用していた時代の産業の規制や資本蓄積のプロセスを説明していた。ハーヴェイにとってのフォーディズムは、アントニオ・グラムシによる語が大量生産や労使関係の方法に関連している点でケインズ主義と関係していたが、経済政策や産業の規制と関係していた。したがってポスト・フォーディズムはハーヴェイの視点によればポストモダニティの基本的な側面の1つを構成していた。
ポストモダニティの産物はテレビやポピュラー・カルチャーによる支配、情報に接する利便性の拡大、マスメディアの役割の拡大を含んでいた。またポストモダニティは環境保護や反戦運動に見られるような進歩の名の下の犠牲に対する抵抗運動を示していた。工業化におけるポストモダニティはフェミニズムや多文化主義のようなムーブメントと同様に公民権運動や他の抵抗運動に焦点を当てていた。政治におけるポストモダンは抑圧や疎外(性や民族における)に対するさまざまな抵抗運動を通じた公民権や政治活動の可能性や多様な場によって特徴付けられていたが、政治におけるモダニストは階級闘争に囚われたままであった。
ミシェル・マフェゾリのような研究者は、ポストモダニティが存在を支える枠組みを崩壊させており、個人主義の弱体化や新部族主義の登場をもたらすだろうと考えていた。
現在の経済状況や技術環境はメディアによって支配されたばらばらな社会を生み出しており、その内容は見せかけにすぎず、相互言及的なアイデアの集合であり、意味に関して客観的な実体のない中身を真似し合う状況であった。意思の疎通、製造プロセス、輸送手段におけるイノベーションによってもたらされたグローバリゼーションはばらばらな近代的生活に拍車をかける推進力のようなものであり、政治・意見交換・知的活動の中心が欠落しており、文化的な複数性を有しており、相互に関連したグローバル・コミュニティを生み出していた。ポストモダニストの視点によれば、客観的とは言いがたい間主観的な知識が支配的な言説になり、情報の普及の偏りによって人々と情報や消費者と生産者の関係が根本的に変化していることが指摘されていた。
『スペース・オブ・ホープ』の中でハーヴェイは、政治におけるポストモダンは(マルキストの意味で)弱者の問題やフォーディズムの時代以上に重要になっていた現在の政治に対する批評の意識に間接的に関係していた。ハーヴェイにとって階級闘争は解決に程遠いものであった(彼の説明によればポストモダニストはこの問題を無視していたのだが)。グローバリゼーションによって権利が保護されない低賃金労働の問題に労働組合が取り組むことが一層困難になっていたのだが、欧米の消費者が支払っている商品の価格と東南アジアの労働者が稼いでいる低賃金のギャップによって企業の収益は一層大きなものになっていた。
5 批判
ポストモダンに対する批判は大きく4つに分かれており、モダニズムを否定する視点を理由にしたポストモダニティに対する批判、ポストモダニティが近代のプロジェクトに含まれる公共性や合理性を欠いていると考えているモダニストによる批判、ポストモダニズムに対する理解に依拠した変化を求めているポストモダニティの内部からの批判、現在の社会を鑑みるとポストモダニティが過去のものになっているといった批判であった。
http://en.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault
ミシェル・フーコー
ミシェル・フーコー(1926年10月15日-1984年6月25日)はフランスの哲学者、思想史の研究者、社会理論の研究者、文学研究者、文芸評論家であった。フーコーの理論は権力と知識の関係に言及しており、どのように権力と知識が組織的に社会統治の道具として用いられてきたのかを示していた。ポスト構造主義者ないしポストモダニストと呼ばれているフーコーはこの呼び名を承諾しておらず、彼の思想がモダニティにおける批評史に分類されることを好んでいた。フーコーの思想は研究者とアクティビスト・グループの双方に大きな影響を与えていた。
ポワチエの上流階級の家庭に生まれ、フーコーはアンリ4世高校で教育を受け、その後エコール・ノルマルで学び、哲学に対する関心が強くなり、ジャン・イポリットやルイ・アルチュセールといった師から影響を受けていた。民間外交官として外国で数年過ごした後、フーコーはフランスに戻り、最初の著作である『狂気の歴史』を発表していた。1960年から1966年にかけてオーベルニュ大学に職を得た後、フーコーは2冊の著作を仕上げ、『臨床医学の誕生』や『言葉と物』がそれらであり、構造主義や後に距離を置くことになる社会人類学に対する関心を示していた。これらの著作は「考古学」と名付けられ歴史を研究するためのアプローチの例を示していた。
1955年から1968年にかけてフーコーはフランスに戻る前にチュニス大学で講義をしており、その後ヴァンセンヌ実験大学の哲学科の教員になった。1970年にフーコーはコレージュ・ド・フランスの教員になり、生涯を通じそのメンバーシップを保持していた。またフーコーは多くの左派グループのアクティビストでもあり、反レイシズム運動、人権擁護運動、刑法改正運動に関わっていた。さらにフーコーは『知の考古学』、『監獄の誕生』、『性の歴史』を発表していた。これらの著作を通じてフーコーは社会的な言説の変化において権力が担っている役割にフォーカスした考古学的ないし系図的アプローチを採用していた。その後パリでフーコーはエイズに付随した神経組織の病気で死去することになり、エイズで亡くなった最初のフランスの公人になり、フーコーのパートナーであるダニエル・ドフェールはエイズ基金を設立していた。
1 若い頃
1.1 青年期:1926年-1946年
ポール=ミシェル・フーコーは1926年10月15日にフランス西部のポワチエで保守的な中産階級の家庭の二番目の子供として誕生していた。フーコーは父であるポール・フーコーに因んで名付けられており、それが家庭の伝統であったが、母は二つの名前から成るファーストネームである「ミシェル」を主張しており、学校では「ポール」であったが、生涯を通じてフーコーは「ミシェル」を好んでいた[3]。フーコーの父(1893年-1959年)は地元の外科医であり、ポワチエに移る前にフォンテーヌブローで生まれており、そこで開業しながら、地元の女性であるアン・マラペールと結婚していた[4]。アン・マラペールは外科医であるプロスペル・マラペールの娘であり、プロスペル・マラペールは開業医でありポワティエ大学の医学部で解剖学を教えていた[5]。ポール・フーコーは義理の父の病院を引き継ぎ、アン・マラペールはヴォンドゥーヴル=デュ=ポワトの村にあるル・ピロワールと呼ばれる19世紀の大きな住居を守っていた[6]。3人の子供であるフランシーヌと名付けられた娘とポール=ミシェルやデニスと名付けられた2人の息子と同様に、彼らは全員金髪で明るい青い目をしていた[7]。子供たちは表面的にはカトリック教徒として育てられており、サン・ポルチェールの教会のミサに参加しており、短期の間ミシェルは侍祭の役を務める少年であったが、家族は敬虔ではなかった[8]。
その後の人生を通じてフーコーは少年時代についてほとんど語ることがなかった[10]。「非行少年」であったと述べながら、フーコーは彼の父が厳しい罰を与えるいじめを行なっていたと主張していた[11]。1930年にフーコーは地元のアンリ4世高校で2年早く学校生活を始めていた。フーコーは2年間でリセに入る前の初等教育を終えており、リセには1936年まで在籍していた。そして同じ学校での中等教育を4年間で終えており、フランス語、ギリシア語、ラテン語、歴史を得意としながらも、数学が苦手であった[12]。1939年に第二次世界大戦が始まり、1945年までフランスはナチスドイツに占領されていた。フーコーの両親はドイツによる占領とヴィシー政権に反対していたが、レジスタンスには参加していなかった[13]。1940年にフーコーの母はイエズス会によって運営されていた厳格なカトリックの機関であるサン・スタニスラス学院にフーコーを通わせていた。フーコーはそこでの生活を「厳しい試練」と表現していたが、特に哲学、歴史、文学において優れた成績であった[14]。1942年にフーコーは最終学年になり、哲学の研究に専念しながら、1943年にバカロレアに合格した[15]。
地元のアンリ4世高校に戻り、1年間フーコーは歴史と哲学を研究しており[16]、哲学者であるルイ・ジラールから助力を得ていた[17]。そしてフーコーを外科医にさせる父の希望を否定しており、1945年にフーコーはパリに行き、アンリ4世高校として知られている最も有名な中等学校の1つに通っていた。またフーコーは哲学者であるジャン・イポリットの下で研究しており、ジャン・イポリットはヘーゲルやカール・マルクスの弁証法と実存主義を融合させる19世紀ドイツの哲学者であるヘーゲルの研究の専門家であり、実存主義者であった。これらの思想はフーコーに影響を与えており、哲学は歴史の研究を通じて研究されなければならないといったイポリットの信念をフーコーは受け継いでいた[18]。
1.2 エコール・ノルマル:1946年-1951年
優秀な成績で1946年の秋にフーコーはエコール・ノルマル(ENS)に入学していた。入学のためにフーコーはジョルジュ・カンギレムとピエール・マクシム・シュールから口頭試問を受けていた。ENSに入学した100名の内、フーコーは入学試験の結果では上から4番目で、高い競争率を経験していた。多くのクラスメイトと同じ様にフーコーはユルム街の寄宿舎で暮らしていた[19]。フーコーは人気がない学生で、1人で過ごすことが多く、貪欲に読書をしていた。フーコーの友人たちは暴力やグロテスクなものに対するフーコーの執着心に感づいていた。フーコーはスペインの芸術家であるフランシスコ・デ・ゴヤがナポレオン戦争の時に描いた拷問や戦争の挿し絵を使って寝室を装飾しており、時として仲間を短剣で追い回していた[20]。伝聞によればフーコーは自殺に失敗しており、それを理由にしてフーコーの父はサンタンヌ病院の精神科医であるジャン・ディレイの所にフーコーを連れていった。自傷行為や自殺行為が後をひき、フーコーは何度かそれらを繰り返しており、後年の著作の中で自殺行為を肯定していた[21]。ENSの医師はフーコーの精神状態を鑑定しており、フーコーの自殺の傾向がホモセクシュアリティに対する悩みに起因しており、同性間の行為が当時のフランスでタブーであったことが背景に存在していた[22]。またフーコーは薬物の使用を含めてパリのゲイとの行為に耽ることがあった。伝記作家のジェームス・ミラーによれば、フーコーは危険な行為のスリルを楽しんでいた[23]。
さまざまなテーマを研究しているにもかかわらず、フーコーの関心は哲学にあり、ヘーゲルやマルクスだけでなく、イマヌエル・カント、エトムント・フッサール、特にマルティン・ハイデッガーを読み込んでいた[24]。フーコーは哲学者であるガストン・バシュラールの著作を読み始めており、科学史の研究に関心を示していた[25]。1948年に哲学者であるルイ・アルチュセールがENSのチューターになった。マルキストであるルイ・アルチュセールはフーコーや他の多くの学生達に影響を与えており、彼らをフランス共産党(PCF)に勧誘していた。1950年にフーコーはフランス共産党に入党していたが、特別な活動をしていた訳ではなく、マルキストの視点を取り入れたこともなく、階級闘争のようなマルキストの教義に対して反論していた[26]。フーコーはすぐに共産党で経験した偏狭さに不満を抱くようになっていた。個人的にフーコーは同性愛恐怖症を経験しており、ソ連共産党幹部暗殺計画を通じて示されていた反ユダヤ主義に恐怖を感じていた。1953年にフーコーは共産党から離党したが、アルチュセールとの親交はそのままであった[27]。1950年に1回失敗したけれども、1951年の2回目に哲学のアグレガシオンに合格した[28]。医学的な観点から兵役を免除された後、フーコーはティエール財団で博士号のために研究する決意を固めており、それは心理学における哲学にフォーカスしたものであった[29]。
1.3 初期のキャリア:1951年-1955年
その後数年、フーコーはさまざまな研究と教育に携わっていた[30]。1951年から1955年にかけてフーコーはアルチュセールの招きでENSの哲学の講師を務めていた[31]。パリでフーコーは兄弟とアパートをシェアしており、フーコーの兄弟は外科医になる研修を受けていたが、フーコーは1週間の内3日間は北部の都市であるリールに通勤しており、1953年から1954年までリール・ノール・ド・フランス大学で心理学を教えていた[32]。フーコーの講義は多くの学生から好意的に見られていた[33]。一方でフーコーは学位論文を執筆しており、イワン・パブロフ、ジャン・ピアジェ、カール・ヤスパースのような心理学者の著作を読み込むために毎日フランス国立図書館に通っていた[34]。サンタンヌ病院の精神科での研究を引き受け、フーコーは非公式のインターンになり、医師と患者の関係について研究しており、脳波検査室での研究を支援していた[35]。フーコーは精神科医であるジークムント・フロイトによる理論の多くを採用しており、自己の夢に対して精神分析を行い、仲間にロールシャッハ・テストを行なっていた[36]。
またアヴァンギャルドなパリ市民を自認しており、フーコーは作曲家であるジャン・バラケとのロマンスに浸っていた。彼らは人間の思考力の限界を拡大し、最も素晴らしい作品を制作しようとしていた。重度の薬物依存であり、彼らはサドマゾの関係にあった[37]。1953年8月にフーコーとバラケはイタリアで休暇を過ごしており、ドイツの哲学者であるフリードリヒ・ニーチェによる4編のエッセイから構成されていた『反時代的考察』(1873-1876)に耽っていた。後にニーチェの著作を「啓示である」と表現したフーコーは著作を深く読み込むことが自身に影響を与えていたと感じており、読書が転機になっていた[38]。そして1953年にフーコーはサミュエル・ベケットの『ゴドーを待ちながら』のパリ公演を観劇したときに新たな自己を見出していた[39]。
文学に関心があり、フーコーは『新フランス評論』における哲学者であるモーリス・ブランショによる書評の熱心な読者であった。ブランショの文体や批評理論に魅了されており、後期の作品の中でフーコーは自身を「取材・検討する」ブランショのアプローチを取り入れていた[40]。またフーコーはヘルマン・ブロッホによる『ウェルギリウスの死』(1945年)に出会い、それはフーコーとバラケを魅了していた。バラケは『ウェルギリウスの死』をエピック・オペラにしようとしていたが、フーコーは人生を肯定した死の描写を理由にしてブロッホの文章を賞賛していた[41]。フーコーとバラケはマルキ・ド・サド、フランツ・カフカ、ジャン・ジュネのような作家の作品に対しても関心を抱いており、それらは性と暴力をテーマにしていた[42]。
そしてスイスの精神科医であるルートヴィヒ・ビンスワンガーの著作に関心を示しており、フーコーは友人であるジャクリーヌ・ヴェルドーがその作品をフランス語に翻訳することを支援していた。特にフーコーは自殺するに至ったエレン・ウェストに対するビンスワンガーの研究に関心を抱いていた[44]。1954年にフーコーはビンスワンガーの論文である『夢と実存』のイントロダクションを執筆しており、夢が「世界の誕生」と「剥き出しの感情」で構成されており、理性の奥深い欲望を表していると主張していた[45]。同じ年にフーコーは最初の著作である『精神疾患と心理学』を出版しており、その著作の中でマルキストやハイデッガリアンの思想からの影響を示しており、パブロフの反射理論による心理学からフロイトによる古典的な精神分析まで幅広いテーマを扱っていた。エミール・デュルケームやマーガレット・ミードのような社会学者や人類学者の著作を引き合いに出しながら、フーコーは病気が文化と関連しているといった理論を示していた[46]。伝記作家であるジェームス・ミラーによれば、その著作は「博識と明白な知性」を示していたが、フーコーがその後の著作で示している「ある種の情熱」に欠けていた[47]。著作は評論として見向きもされていなかったが、当時ただ1つからレビューを受けていた[48]。フーコーはそのことから影響を受けて、英語への翻訳と再版を思いとどまろうとしていたが、そうはならなかった[49]。
1.4 スウェーデン、ポーランド、西ドイツ:1955年-1960年
フーコーはその後の5年間を海外で過ごしており、初めはスウェーデンのウプサラ大学で民間外交官として勤務しており、その仕事は宗教史を専門にしているジョルジュ・デュメジルの知人を通じたものであった[50]。ウプサラでフーコーはフランス文学の助手に着任しており、同時にメゾン・ド・フランスのディレクターとして勤務しており、それをきっかけにして民間外交官のキャリアを切り開いていた[51]。北欧の薄暗く長い冬を気に入っていなかったが、フーコーは生化学者であるジャン・フランソワ・ミケルや物理学者であるジャック・パーペ=レピーヌと親しくなり、さまざまな人々とロマンスに耽っていた。ウプサラではフーコーは大酒飲みで知られており、ジャガーを乗り回していた[52]。1956年の春にバラケはフーコーとの関係を終わりにし、「狂気のなせる混乱」から逃れたいと告げていた[53]。ウプサラでフーコーは大学のカロリーナ・レディヴィヴァ・ライブラリーで長時間を過ごしており、医学史の研究のためにビブリオテーカ・ワレリアーナ・コレクションを利用していた[54]。医学論文を執筆し終え、フーコーはウプサラ大学に論文が受理されることを願っていたが、科学史を専門にしているステン・リンドロスは否定的な見解を示し、推論の一般化が多く歴史としては中途半端であると主張していた。ステン・リンドロスはウプサラ大学で博士号を出すことに反対しており、それを理由にしてフーコーはスウェーデンを去ることになった[55]。
デュメジルに認められて、1958年10月にフーコーはポーランドのワルシャワに到着し、ワルシャワ大学のフランス語センターに着任した[56]。第二次世界大戦の荒廃に伴う物資やサービスの欠乏により、フーコーはポーランドでの生活における困難に直面していた。学生が共産主義のポーランド統一労働者党による支配に抗議していたポーランド十月革命の結末を目の当たりにして、フーコーは多くのポーランド人がソ連の傀儡としてのポーランド政府を軽蔑していたことを感じ取っており、システムが「誤って」機能していると考えていた[57]。大学を自由の場として考えており、フーコーは自由に講義ができる国に移ることになった。その評判を示すことによって、フーコーは事実上の文化担当官に着任していた[58]。フランスやスウェーデンでは同性愛は合法であったが、ポーランドでは社会的に肩身が狭いものであり、フーコーは多くの男性と交友しており、1人はフーコーを罠にかけるためのポーランドのエージェントであり、そのことがフランス大使館に悪影響を及ぼしていた。外交上のスキャンダルに苦しめられて、フーコーはポーランドから次の地へ移ることになった[59]。さまざまな立場が西ドイツにはあり、フーコーはハンブルクに移りウプサラやワルシャワで担当していたコースを受け持つことになった[60]。そしてレーパーバーンで多くの時間を過ごしており、フーコーは女装の趣味を有する人々との交友を広げていた[61]。
2 円熟期のキャリア
2.1 『狂気の歴史』(1960年)
西ドイツでフーコーは博士論文を仕上げ、その学位論文である『狂気の歴史』は医学史に対する彼の研究に依拠していた。その著作はどのように西欧社会が狂気を取り扱ってきたのかを論じており、その西欧社会は精神疾患の人々から完全に切り離されたものであったと論じていた。フーコーは3つのフェーズを通じた狂気の概念の展開をトレースしており、それらはルネサンス、17世紀から18世紀、近代を指していた。その著作はフランスの詩人であり劇作家であるアントナン・アルトーの作品を想起させており、アントナン・アルトーは当時のフーコーの思想に大きな影響を及ぼしていた[63]。
『狂気の歴史』は包括的な著作であり、それは943ページからなり、付録と参考文献一覧が付随していた[64]。フーコーはパリ大学に学位論文を提出していたが、博士号を授与するための学則は主要な論文と補足的な論文の双方を提出することを求めていた[65]。当時のフランスで博士号を取得することは多段階のステップを必要としていた。最初のステップはラポーターと著作のスポンサーを探すことであり、フーコーはジョルジュ・カンギレムを選んでいた[66]。二番目のステップは出版社を探すことであり、『狂気の歴史』はガリマール出版社に拒否された後にフランス大学出版局を通じてフーコーが選んだプロン出版社から1961年5月にフランス語で出版されることになった[67]。1964年に簡約版がペーパーバックで出版され、翌年英語に翻訳されることになった[68]。
『狂気の歴史』はフランスでの出来事にフォーカスした外国誌やフランスでさまざまな受けとめ方をされていた。ブローショ、ミシェル・シェール、ロラン・バルト、ガストン・バシュラール、フェルナン・ブローデルによって賞賛されていたが、フーコーを悩ませていたことに『狂気の歴史』が左派による論壇から無視されていたことが挙げられていた[69]。『狂気の歴史』は形而上学を支持していたことを理由にして1963年3月のパリ大学での講義の中で若手の哲学者であるジャック・デリダによって批判されていた。悪意に満ちた返事に対して、フーコーはデリダの論点を無視することで対抗しており、デリダの主張はルネ・デカルトに対するフーコーの解釈を批判することに焦点を絞っていた。1981年に和解するまで2人は険悪なままであった[70]。英語圏では『狂気の歴史』は1960年代の反精神医学運動に大きな影響を与えていた。フーコーは反精神医学運動に対して入り混じったアプローチを採っており、多くの反精神医学者に影響を及ぼしていたが、彼らの多くが『狂気の歴史』を誤解していると主張していた[71]。
フーコーの副論文はドイツの哲学者であるイマヌエル・カントによる『実用的見地における人間学』(1798年)を翻訳し注釈を付したものであった。カントのテクストにおける考古学といったテクストの時代設定を論じたフーコーによる議論で構成されており、フーコーは哲学的に大きく影響を受けていたニーチェを想起しながら論文を纏めていた[72]。この著作におけるラポーターは昔のチューターとENSのディレクターであるイポリットになり、イポリットはドイツの哲学者によく知られた存在であった[64]。これらの2つの論文がレビューされた後、フーコーはディフェンスを組み立て、1961年5月20日に口頭審査を受けることになった[73]。フーコーの著作をレビューした研究者はフーコーの主論文の型破りな特徴に懸念を示しており、レビュアーであるアンリ・グイエはフーコーの主論文が歴史におけるお約束の原稿でないことを指摘しており、その著作が十分な各論を展開しないで包括的な一般化を行っており、フーコーが「寓意を用いて論理を展開している」ことを付け加えていた[74]。しかしレビュアーはそれらの論文が優れていることを認めており、「留保を付けながら」、フーコーに博士号を授与していた[75]。
2.2 オーベルニュ大学、『臨床医学の誕生』、『言葉と物』:1960年-1966年
1960年10月にフーコーはオーベルニュ大学の哲学の講座でテニュアを得て、毎週パリからクレルモン=フェランへ通勤しており[76]、パリのファンレイ街の高層住宅で暮らしていた[77]。哲学科で心理学を教えることを担当しており、フーコーはオーベルニュ大学では「面白い」が「やや型にはまった」教員と考えられていた[78]。哲学科はジュール・ヴュイユマンによって運営されており、ジュール・ヴュイユマンはフーコーとすぐに親しくなっていた[79]。1962年にヴュイユマンがコレージュ・ド・フランスの教員に選任された後、フーコーはヴュイユマンの仕事を引き継いでいた[80]。このポジションに就いてからフーコーはあるスタッフを嫌っており、その軽視されていたスタッフの中にフランス共産党の幹部であるロジェ・ガロディが含まれていた。フーコーはガロディによって大学での人生が危うくなっており、ガロディをポワチエに移籍させていた[81]。またフーコーは哲学者であるダニエル・ドフェールのために大学での仕事を確保したために論争を引き起こしており、ダニエル・ドフェールと一夫一婦制の枠に収まらない関係を続けていた[82]。
フーコーは文学に対する関心を失っておらず、文学雑誌である『テル・ケル』や『新フランス評論』にレビューを載せており、『クリティーク』の編集委員を務めていた[83]。1963年5月にフーコーは詩人、作家、脚本家であるレーモン・ルーセルに捧げた著作を出版していた。それは2ヶ月で書き上げられており、ガリマール出版社から出版され、伝記作家であるデイビット・メイシーによってルーセルの著作との「特別な関係」から生じた「内輪の著作」として紹介されていた。その著作は1983年に『死と迷宮:レーモン・ルーセルの世界』として英語で出版されていた[84]。レビューはほとんどなく、それはほぼ無視されていた[85]。同じ年にフーコーは『狂気の歴史――古典主義時代における』の続編である『ネサーンス・ドゥ・ラ・クリーニク』を発表しており、後にそれは『臨床医学の誕生』として翻訳されていた。前作より短く、『臨床医学の誕生』は18世紀後半から19世紀初頭の医学界の変遷にフォーカスしていた[86]。前作のように『ネサーンス・ドゥ・ラ・クリーニク』は批評の対象から外されていたが、後に一時の熱狂を獲得することになった[85]。またフーコーは1963年11月から1964年3月まで国民教育大臣であるクリスティアン・フーシェによって指揮された大学改革を議論するために招集された「18人委員会」の委員に選ばれていた。大学改革は1967年に行われており、スタッフによるストライキや学生による抗議活動に発展していた[87]。
1966年4月にガリマール出版社はフーコーの『言葉と物』を出版しており、後に英語に翻訳していた[88]。どのように人間が知の対象になっていったのかを研究しながら、『言葉と物』は、あらゆる時代の歴史が科学のディスコースとして容認できるものを形成している真実の背後にある特定の状況を示唆していることを論じていた。フーコーはこれらの真実の背後にある特定の状況がある時代のエピステーメーから次の時代のエピステーメーへと変化してきたと述べていた[89]。専門家向きの著作であったけれども、それはメディアから注目を集めて、フランスのベストセラーになった[90]。新たな思想家がジャン=ポール・サルトルによって人気を博していた実存主義を一掃したことから、構造主義に対する関心が高まり、フーコーは研究者であるジャック・ラカン、クロード・レヴィ=ストロース、ロラン・バルトと共に行動していた。当初はこういった説明を容認していたが、フーコーはすぐにそうした説明を激しく否定していた[91]。フーコーとサルトルはメディア上で互いを批判し合っており、サルトルとシモーヌ・ド・ボーヴォワールは「中産階級」に立脚したフーコーの思想を批判していたが、フーコーは「マルクス主義は19世紀の思想としては妥当であったのだが、現在は死に絶えているに等しい」と述べることによってマルキストの信念に対して反論していた[92]。
2.3 チュニス大学とヴァンセンヌ大学:1966年-1970年
1966年9月にフーコーは北アフリカのチュニス大学で心理学を教えることになった。その決定は主にドフェールが兵役でチュニジアに赴任することを理由にしていた。フーコーはチュニスからシディ・ブ・サイドまで数キロメートル移動しており、シディ・ブ・サイドには研究者仲間のジェラルド・デレダルが奥さんと共に暮らしていた。到着してすぐにフーコーはチュニジアが「歴史に恵まれた国」であることに触れており、「ハンニバルやアウグスティヌスが暮らしていた土地でもあるので、永住する価値がある」と述べていた[94]。フーコーの講義は人気があり、出席者が多かった。多くの学生がフーコーの講義に夢中になり、保守派の政治観であると考えていたものに対して批判的になり、フーコーを「ド・ゴール派のテクノクラシーの代表」として眺めていたが、フーコーは自身を左派として捉えていた[95]。
フーコーは1967年の反政府・親パレスチナの暴動がチュニスに衝撃を与えた頃のチュニスに滞在しており、その暴動は1年間続いていた。多数の抗議者による暴力、極右、反ユダヤ主義に対して批判的であったけれども、フーコーは自身の立場を用いて過激派左翼の学生の一部がアジで逮捕され拷問にあうことから救おうとしていた。フーコーは自宅の庭に学生の印刷物を隠して、学生に対する裁判で学生を擁護するために証言しようとしていたが、裁判が非公開になったためにそれはなくなった[96]。チュニスに滞在している間フーコーは執筆し続けていた。シュルレアリスムの画家であるルネ・マグリットとの文通に触発されて、フーコーは印象派の画家であるエドゥアール・マネについての本を執筆し始めていたが、それは未完に終わった[97]。
1968年にフーコーはパリに戻り、ヴォージラール通り沿いのアパートに引っ越していた[98]。フランスの五月革命以後、国民教育大臣であるエドガー・フォーレは自治を拡大した新たな大学を設立することによる教育改革を決定していた。この改革で最も有名なものはパリ郊外のヴァンセンヌにあるヴァンセンヌ実験大学であった。著名な研究者のグループに対してヴァンセンヌ実験大学を運営するための教員を選ぶようにとの要請があり、カンギレムは哲学部長としてフーコーを推薦していた[99]。ヴァンセンヌでテニュアを持った教員になり、フーコーの希望はその学部で「今のフランス哲学でのベスト」の布陣を敷くことであり、ミシェル・セール、ジュディス・ミラー、アラン・バディウ、ジャック・ランシエール、フランソワ・ルニョー、アンリ・ウェーバー、エティエンヌ・バリバール、フランソワ・シャトレを採用しており、彼らの多くはマルキストや極右活動家であった[100]。
1969年1月から大学での講義が始まったのだが、学生やフーコーを含むスタッフが占拠や警察との衝突に巻き込まれて、逮捕されてしまっていた[101]。2月にフーコーはミュチュアリテのカルチェラタンでの抗議活動に対する警察の挑発を非難する演説を行なっていた[102]。そのような活動はフーコーによる極左に対する支援として特徴付けられており[103]、確かにドフェールの影響であり、ドフェールはヴァンセンヌ実験大学社会学部で職を得ており、毛沢東主義者であった[104]。フーコーの哲学科で提供しているコースの多くはマルクス・レーニン主義を指向していたが、フーコー自身はニーチェの『形而上学の終焉』や『セクシュアリティの言説』のコースを担当しており、それらは人気が高く、定員を大幅に超過していた[105]。右派のプレスがこの新しい組織や制度を批判していたけれども、新しい国民教育大臣であるオリヴィエ・ギシャールはその理念の歪みや無試験であることに立腹しており、学生は何ら考えることなく学位を与えられていた。オリヴィエ・ギシャールは学位の国家認定を拒否しており、フーコーは公開の場で反論していた[106]。
3 その後の生活
3.1 コレージュ・ド・フランスと『監獄の誕生』:1970年-1975年
フーコーはヴァンセンヌ実験大学を離れることを希望して、コレージュ・ド・フランスの一員となった。フーコーはその一員となることに関して『思考システムの歴史』と呼ばれる講座を担当することを希望しており、そのフーコーの案はデュメジル、イポリット、ヴュイユマンから支持されることになった。1969年11月に公募が始まり、フーコーはコレージュの一員に選ばれることになったが、ラージ・マイノリティはその選出に反対していた[107]。1970年12月の講義がその初回になり、『言説表現の秩序』として出版されていた[108]。フーコーは年12週の講義を担当し、以後それが続くことになり、当時フーコーが研究していたトピックスを取り上げていた。フーコーの講義は「パリっ子の知的生活におけるひとコマ」になり、頻繁に定員を超えていた[109]。毎週月曜日にフーコーは学生向けのゼミを開いており、その多くが「フーコディアン」になり、フーコーと共に研究していた。フーコーは学生との共同研究を楽しんでおり、共同で多くの短編を出版していた[110]。コレージュでの研究はフーコーの活躍の場を広げることになり、ブラジル、日本、カナダ、アメリカで14年以上講演を行なっていた[111]。
1971年5月にフーコーは歴史家であるピエール・ヴィダル=ナケやジャーナリストであるジャン=マリー・ドームナクと共に監獄情報グループ(GIP)を共同設立していた。GIPの目的は監獄の劣悪な環境を調査し公開し、フランス社会で囚人や元囚人が発言権をもてるようにすることであった。彼らは刑罰のシステムに批判的であり、刑罰のシステムが軽犯罪を重罪に変えてしまうと考えていた[112]。GIPは記者会見を行い、他の刑務所の暴動に伴った1971年12月のトゥール刑務所の暴動についての出来事に対して抗議をしており、それを理由にして彼らは警察によるガサ入れや逮捕を味わうことになった[113]。GIPはフランス全土で活動しており、メンバーは2,000人から3,000人前後いたが、1974年以前に解散することになった[114]。死刑に反対するキャンペーンを行い、フーコーは処刑された殺人の加害者であるピエール・リヴィエールの事例についての短編を共著していた[115]。刑罰のシステムを研究しながら、1975年にフーコーは『監獄の誕生』を出版しており、西欧における監獄システムの歴史を描き出していた。伝記作家であるディディエ・エリボンは『監獄の誕生』をフーコーの著作の中で「最も秀逸なもの」として示しており、評論家の中でも好意的に受けとめられていた[116]。
またフーコーは反レイシズム運動に参加しており、1971年11月に明らかなレイシストがアラブからの移民であるドゥジュラリ・ベン・アリを殺害したことに対して抗議するリーダーの1人になった。この運動においてフーコーはかつてのライバルであるサルトル、ジャーナリストであるクロード・モーリアック、作家の1人であるジャン・ジュネとともに活動していた。この運動はル・コミテ・ドゥ・デファンス・ドゥ・ラ・ヴィ・エ・デ・ドゥロワ・デ・トラヴァイユール・イミグレ(CDVDTI)を形成していたが、フーコーが多くのアラブ人労働者や毛沢東主義者による反イスラエル感情に反論していたので、その会合にはある緊張が存在していた[117]。1972年12月に警察がアラブ人労働者であるモハメド・ディアブを殺害したことに対する抗議活動で、フーコーとジュネは逮捕されており、その経緯が広く世に知られることになった[118]。またフーコーはアージャンス・ドゥ・プレス・リベラシォン(APL)の設立に関与しており、それは左派のジャーナリストのグループであり、メインストリーム・メディアで無視されているニュースを伝えることを目的にしていた。1973年に彼らは日刊紙のリベラシオンを設立し、フーコーは彼らがニュースを収集し報道を提供するためにフランスをカバーするリベラシオン委員会を創設することを提案しており、『プー・ユヌ・クローニク・ドゥ・ラ・メモワール・ウーヴリエール』として知られるコラムを投稿し、労働者が意見を表明することを受け入れていた。フーコーは新聞に活動的なジャーナリズムを求めていたがその活動を擁護し切れないと考えてからリベラシオンに幻滅しており、その理由として報道が事実を歪めていることを指摘しており、1980年までコラムを投稿することはなかった[119]。
3.2 『性の歴史』とイラン革命:1976年-1979年
1976年にガリマール出版社はフーコーによる『性の歴史』を出版しており、その小著はフーコーが「抑圧に対する仮説」と呼んでいる枠組みを探求していた。その著作は権力の概念を巡る分析を展開しており、フーコーは精神分析や権力に対するマルキストの理論を否定していた。フーコーはそれらのテーマに対する7分冊の内の初めの1冊として『性の歴史』を位置付けていた[120]。それはベストセラーになりプレスから好意的な評価を受けていたが、一方で知識層の無関心がフーコーの悩みであり、彼らの多くはフーコーの仮説に対して誤解を抱いていた[122]。フーコーはシニアスタッフであるピエラ・ノヴァから不快感を与えられガリマール出版社に対して不満を抱くなるようになった[122]。ポール・ベイヌとフランソワ・ヴァールとともにフーコーはソイル社を通じて『デ・トラヴォー』として知られる専門書の新たなシリーズに着手しており、フランスにおけるアカデミズムの改善を願っていた[123]。またフーコーはエルキュリーヌ・バルバンによる手記の序文を書いていた[124]。
フーコーは政治的なアクティビストであり続け、国内外の政府による人権侵害を注視していた。フーコーはスペイン政府が公正な裁判を行わずに11名の過激派を処刑したことに対する1975年の抗議活動において中心的な役割を果たしていた。彼らは記者会見を行うために6名の仲間とともにマドリードに到着したが逮捕されパリに送還されることになった[126]。1977年にクラウス・クロワッサンを西ドイツに引き渡すことに抗議していたときに、フーコーは機動隊との衝突で肋骨を骨折していた[127]。また1977年7月にソ連の共産党書記長であるレオニード・ブレジネフがパリを訪問したことに合わせて、フーコーは東側の反体制派の集会を組織しており[128]、1979年にはベトナムの反体制派がフランスに亡命することに対して賛同を示す運動を展開していた[129]。
1977年にイタリアの新聞であるコリエーレ・デラ・セラはフーコーにコラムを依頼していた。そしてフーコーはイラン革命におけるブラック・フライデーの直後になる1978年にテヘランに渡っていた。イラン革命の展開を記事にしながら、フーコーはムハンマド・カゼム・シャリアトマダリやメフディー・バーザルガーンのような対抗勢力のリーダーに会うことを通じてイスラム主義に対する国民的な支持を見出していた[130]。フランスに帰国するとフーコーはルーホッラー・ホメイニーと会ったことのあるジャーナリストの1人になっており、それは再度テヘランを訪問する以前のことであった。フーコーによる記事はホメイニーによるイスラム主義運動に対する敬意を示しており、それを理由にリベラル派のイラン反体制派やフランスのメディアから批判を受けることになった。それに対するフーコーの回答はイスラム教が中東において大きな政治的影響力を有するべきであり欧米は敵対的な姿勢よりむしろ敬意をもってイスラム教に接するべきであるといったことであった[131]。1978年4月にフーコーは日本を訪問しており、上野原にある青苔寺で大森曹玄を通じて禅宗を研究していた[111]。
3.3 晩年:1980年-1984年
力関係に対する批判を継続していたけれども、フーコーは1981年の総選挙によって成立したフランソワ・ミッテランによる社会党政権に対する支援を自重しながら表明していた[132]。しかし社会党政権に対するフーコーの支援は社会党政権が1982年に行われた連帯によるデモに対するポーランド政府による弾圧を非難することを拒んだとき以降変質していった。フーコーと社会学者であるピエール・ブルデューはミッテランの不作為を非難する文書を執筆しており、それはリベラシオン紙上で公表され、フーコー達は社会党政権の不作為に対する幅広い抗議活動に参加していた[133]。フーコーは連帯に対する支援を継続しており、仲間であるシモーヌ・シニョレとともに「世界の医療団」のメンバーとしてポーランドに渡り、アウシュビッツ強制収容所を訪問していた[134]。またフーコーは学術調査を継続しており、1984年6月にガリマール出版社は『性の歴史』の第2巻と第3巻を出版していた。第2巻の『快楽の活用』は倫理に関連した古代ギリシアの一般市民の道徳によって規定されている「テクニーク・ドゥ・ソワ」を扱っており、第3巻の『自己への配慮』は西暦200年までのギリシアやローマのテクストにおける同様のテーマを探求していた。第4巻の『肉の告白』は初期のキリスト教における同じテーマを追求していたが、フーコーの死によって未完で終わった135]。
1980年10月にフーコーはUCバークレーの客員教授になり、「真実と主観性」について講義を行い、11月にはニューヨーク大学のヒューマニティーズ・インスティチュートで講義を担当していた。アメリカの知的サークルにおけるフーコーの人気はタイム誌によって取り上げられており、その当時1981年にフーコーはUCLAで講義を行なっており、1982年にはバーモント大学、1983年には再度バークレーで講義を担当しており、その講義は学生で満員であった[136]。カリフォルニアにいた頃フーコーはサンフランシスコ・ベイエリアのゲイ・シーンでよく夜を過ごし、サドマゾ・クラブによく通い、常連との関係が深かった。フーコーはゲイメディアにおけるインタビューの中でサドマゾを肯定しており、それを「新たな楽しみの一環」として認識していた[137]。この当時の関係を通じてフーコーはHIVに感染し、それがAIDSに至っていた。当時はそのウイルスについて分かっていることがほとんどなく、最初の症例は1980年になって漸く認識され始めていた[138]。1983年の夏にフーコーはよく空咳をしており、パリの友人は心配していたが、フーコー自身は単なる肺感染のせいだと主張していた[139]。入院して漸くフーコーは正式な病名を知らされ、抗生物質を処方される中、コレージュ・ド・フランスで連続最終講義を行なっていた[140]。フーコーはサルペトリエール病院に入院しており、『狂気の歴史』の中でその病院を研究していたのだが、1984年6月9日に敗血症に付随した神経症状を呈していた。そして6月25日にフーコーは病院で永眠につくことになった[141]。
6月26日にリベラシオン紙はフーコーの他界を公表しており、それがAIDSによってもたらされていたことに言及していた。翌日ルモンドはHIV/AIDSに言及していないがフーコーの家族によって明らかにされていた経緯についての記事を報じていた[142]。6月29日にフーコーの葬儀が行われ、棺は病院の安置室から運ばれていた。アクティビストや研究者を含む数百人が参列しており、ジル・ドゥルーズは『性の歴史』からの一節を引用しながら式辞を述べていた[143]。その亡骸はささやかにヴォンドゥーヴルの地に埋葬されていた[144]。その後フーコーのパートナーであったダニエル・ドフェールはフランスのHIV/AIDSに関する最初の組織であるAIDESを創設しており、その名称はフランス語で「援助(複数形)」を意味する「aides」と頭字語であるAIDSの語呂合わせに由来していた[145]。フーコーの一周忌にドフェールはカリフォルニアを拠点にしているゲイ・マガジンである『ジ・アドヴォカット』を通じてフーコーの死がエイズに関連していたことを公表していた[146]。
4 私生活
フーコーを最初に取り上げた伝記作家であるディディエ・エリボンはフーコーを「複雑で多面性のある個性の持ち主」として描いており、「常に1つの表情の下に別の表情が隠れている」とコメントしていた[147]。またエリボンはフーコーが「研究に対する大きな潜在能力」を顕在化させていると記していた[148]。ENSでのフーコーのクラスメートはフーコーを「常にごった煮を抱えた理解しづらい人物」もしくは「感情に突き動かされる労働者」と評していた[149]。しかしフーコーのパーソナリティーは年を取るにつれて変化を示しており、エリボンによればフーコーは「若さにもがいて」いたが、1960年代以降「輝き」を示してリラックスしながら周囲に幸せを与え始めており、一緒に仕事をしている人々によればダンディな存在であった[150]。1969年にエリボンはフーコーが「闘う知識人」の思想を体現していると記していた[151]。
フーコーはクラシックのファンで、特にヨハン・ゼバスティアン・バッハやヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトを好んでいた[152]。またフーコーはタートルネックのセーターを着ることでよく知られていた[153]。フーコーの死後、友人であるジョルジュ・デュメジルはフーコーのことを「深い思いやりをもちながら」、「文字通りの限界を知らない知性」を示してきた人間として描いていた[154]。
政治に関してフーコーは生涯を通じて左派の立場であったが、そのスタンスはしばしば変化していた。1950年代の前半においてフーコーはフランス共産党のメンバーであったが、正統派マルクス主義の視点に立ったことは一度もなく、3年後に共産党を去り、その理由として共産党内のハイアラーキーにおけるユダヤ人とLGBTに対する偏見に嫌悪感を抱いていたことが挙げられていた。当時ポーランド統一労働者党によって支配されていた社会主義国家であるポーランドでの勤務を経てフーコーは共産主義者のイデオロギーに対して一層幻滅することになった。その帰結として1960年代前半にフーコーは「強烈な反共産主義者」であるとして批判されていたが[155]、多くの学生や同僚とともにマルクス主義の運動に深く関与していた。
5 思想
フーコーの同僚であるピエール・ブルデューはフーコーの思想を「社会の限界を超える逸脱者の旅であり、いつも知識と権力を結びつけていた」と纏めていた[156]。
レディング大学の哲学者であるフィリップ・ストークスは、フーコーの仕事が「薄暗く悲観主義的」なものであるが、それは楽観論の余地を残していたと述べており、その理由として権力によって支配されている領域を強調するためにどのように哲学の訓練が活用されることができるのかをそれが示していることを挙げていた。ストークスによれば、哲学の訓練を通じて、私たちはどのように支配されているのかを理解することができるようになり、権力によって支配されるリスクを最小化する社会構造を構築するための努力を積み重ねることが可能になるといったことが指摘されていた[157]。この延長線上に細部に注意を払うことが含まれており、この細部が人々に個性をもたらしていた[158]。
5.1 文学
哲学に関する著作に加えて、フーコーは文学の仕事もしていた。1963年に『死と迷路 レーモン・ルーセルの世界』が出版され、1986年に英語に翻訳されていた。それは文学におけるフーコーの唯一の単行本であった。その著作についてフーコーは「イージーに楽しみながら短期間で書き上げることができた」と述べていた[159]。フーコーは実験的作品に関する最初の著者の1人であるレーモン・ルーセルのテクストを参照しながら理論、評論、心理学を探求していた。
6 影響
権力や言説に対するフーコーの議論は多くの評論家を触発しており、彼らは権力構造に対するフーコーの分析が不平等に対する闘いを支援していると考えていた。また彼らは、言説分析を通じてハイアラーキーが明らかにされ、ハイアラーキーを正当化している知識の該当分野を分析することによってそれに対する疑念が提起されるかもしれないと主張していた。このことはフーコーの仕事が批評理論に関連していることの表れの1つであった[160]。
2007年にフーコーはフランスの哲学者における「ISI Web of Science」によって人文科学における最も引用された研究者として認められており、「近代の学問に対してこれが示していることはその読者が価値を決定することであり、その評価は読者の視点によって賞賛から失望までさまざまなものになるであろうことが想像されている」とコメントされていた[161]。
6.1 批判
哲学者であるユルゲン・ハーバーマスはフーコーのことを隠れた規範主義者と呼んでおり、フーコーが脱構築している啓蒙時代の原理に暗に依拠していると批判していた(フーコーとハーバーマスの論争を参照せよ)。ハーバーマスが論じている問題の中心はフーコーが研究のアプローチに関してカントとニーチェの哲学の双方を維持しようとしていることの方法にあった。
哲学者であるリチャード・ローティはフーコーの『知の考古学』が基本的に悲観論であり、知の「新たな」理論や知そのものを打ち立てることに失敗していると論じていた。そしてむしろフーコーは歴史を理解することに関するいくつかの貴重な格言を与えており、そのことに関してローティはこう述べていた。
私が理解する限り、フーコーが成し遂げたことは過去を鋭く再度描写したことであり、史料編纂における古い仮定によってトラップに引っ掛かることを避ける方法についての有益なヒントを通じてその描写を補完していたことであった。具体的に言えばそれらのヒントは主に次のようなものであり、「歴史における進歩や意味を期待しないこと、過去の研究や文化のあらゆる要素に関する歴史を合理性や自由の帰結として認識しないこと、そのような研究の本質やその研究の目的を特徴付けるために哲学のボキャブラリーを用いないこと、現在の姿が過去の目標に対する手掛かりを与えていると考えないこと」であった[162]。
哲学者であるロジャー・スクルートンはフーコーが「まやかし」であり、その理由としてフーコーが「よく検討されていない前提を苦労を経た結論として示すために」哲学においてよく知られた問題を探求していたことを挙げていた[163]。
1988年にドイツの歴史家であるハンス=ウルリヒ・ヴェーラーはフーコーのことを激しく批判していた。ヴェーラーはフーコーのことを人文科学や社会科学から良い評価を間違って受けた間違った哲学者と見做していた。ヴェーラーによればフーコーの著作は経験的な歴史の側面において不十分であっただけでなく、しばしば矛盾を含んでおり、明晰さに欠けていた。例えばフーコーによる権力の概念は「しっかりと区分されておらず」、「学界」におけるフーコーの議論はヴェーラーによればフーコーが権威、影響力、権力、暴力、正当性を適切に区別していないときにのみ成立していることを指摘していた[165]。さらにフーコーの議論が論拠となるソースの一方的な選択に基づいており(監獄や精神病棟)、例えば工場のような対象を無視していると論じていた。またヴェーラーはフーコーの「フランス中心主義」を批判しており、その理由としてフーコーがマックス・ヴェーバーやノルベルト・エリアスのようなドイツ系の研究者を考慮に入れていなかったことを挙げていた。そしてヴェーラーはフーコーが「いわゆる実証研究における無数の不備を理由に挙げながら...知的な意味で誠実でなく、実証的に信頼できず、隠れた規範主義者であり、ポストモダニズムに魅了させる研究者」であるとして批判していた[166]。